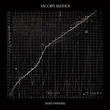NONESUCH × NEW AMSTERDAM
ニュー・アムステルダムの新たなフェーズへ
ノンサッチとの共同リリースによる渾身の3作品
2019年1月、ノンサッチ・レコードとニュー・アムステルダム・レコードのパートナーシップが結ばれた。それはアメリカのクリエイティヴな音楽シーンにとって画期的で、新たな時代の始まりを予兆させる〈事件〉になった。55年目を迎えた名門老舗レーベル、ノンサッチは、つい最近高評価を集めたブラッド・メルドーの渾身作『Finding Gabriel』が出たばかり。そこまで馴染みのない方も、スティーヴ・ライヒ、パット・メセニー、ジョニ・ミッチェル、ビル・フリゼール、デヴィッド・バーンが作品を出している事実からその輪郭がつかめてくるだろう。一方、ニュー・アムステルダムは、既存のジャンルの枠に収まりきれない若手音楽家のための非営利レーベルで、創立2008年ながら、今まで100点以上の作品をリリース。クラシックを基礎としながらも2000年代以降のインディー・ロックや電子音楽とも親和性の高い音楽を精力的に生み出し、NYダウンタウンにあるライヴハウスLe Poisson Rougeと共に、〈インディー・クラシック〉と呼ばれるシーンの中心的存在を担ってきた。互いのレーベルはそれぞれの功績を称え、共同リリースを決定し、ニュー・アムステルダムのエース格のアーティスト3人の作品が選ばれた。

記念すべき1作目はキャロライン・ショウから始まる。そしてその業績は十分に輝かしい。2歳でヴァイオリン、10歳でモーツァルトやブラームスの語法を真似て作曲を始め、ヴァイオリン演奏でライス大学、イェール大学の院まで進学、プリンストン大学の博士では作曲を学んでいる。かと思うとヴォーカリストとしても声楽グループ、ルーム・オブ・ティースで活躍。そこでローリー・アンダーソンやロバート・アシュリーの実験の伝統を感じさせるスポークンワーズや喉歌、囁きなど特殊な歌唱法を精妙に構成した“8声のためのパルティータ”を作曲し、2013年のピューリッツァー賞音楽部門を受賞することになった。ライヒやジョン・アダムズ、オーネット・コールマンらがそれぞれ名声を博してから得た賞を、史上最年少の30歳で受ける快挙だった。拍車をかけるように、2014年に同じルーム・オブ・ティースでグラミー賞の最優秀小規模アンサンブル部門も受賞。すぐにポップフィールドからも声がかかり、カニエ・ウェストの『The Life Of Pablo』や『Ye』、さらにNASの楽曲を共同プロデュースし、ロックバンドのナショナルなどにも参加するなど、まさに息を呑むようなボーダーレスぶり、活躍ぶりを見せている。
そんな彼女が、受賞後に初めてフルアルバムで発表した『Orange』は、長年作曲を続けてきた弦楽四重奏、つまり伝統がある故に実力が試される編成の作品集になった。まず聴かれた方は、表面的には溌剌としたピチカートの多用やリズミカルに洗練されたテクスチャーの選択、機知に富んだ展開があり、飽きのこない音楽的持続が続くことに気付くだろう。さらにその深層には、現代的な視点から、古典的な形式の中における展開や音楽言語の意味性を塗り替えようとする創意がある。参照している伝統は広く、ルネサンス期のジョスカン・デ・プレ、モンテヴェルディからラヴェル、バルトークに到るまであるが、それらは決して表層的な引用に終わらない。彼女の発言に「ハイドンの弦楽四重奏曲のOp.77の第2楽章で、へ長調のメヌエットが変ニ長調のトリオへ移行する際に非常に感銘を受けた」とあるように、時代形式と和声的展開が組み合わさって発生する音楽的な〈妙〉に、いわば作曲家個人のマジックとしか言いようのないものに鋭い耳と感性を持つ。アルバム最初の曲“Entr’acte”はまさにこのハイドン曲にインスパイアされた作品で、最初は3和音をベースにしたシンプルなフレーズから始まり、バルトークを思わせるような濃厚なテクスチャーから打楽器的なピッチのないノイズ音が加わったかと思うと、100年前にはなかった複雑な変拍子、さらにはフィリップ・グラス的アルペジオ、と言う風に、色々な時代背景をめくるめく提示する。再び最初のフレーズに戻ってくるとき、もはや最初とは異なる文脈へと、リスナーは意識を移行させられている。また、ロラン・バルトの「写真論」に影響を受けた“Punctum”は、ノスタルジーをテーマにし、音楽的にはバッハの聖マタイ受難曲における、あるドッペルドミナントにヒントを得たという。転調のシークエンスが文脈から外れて繰り返されることで和声進行の効果を乱すも、終盤においてまたその和声の効力を取り戻す、時間と記憶に関する作品。2000個目のオレンジに出会ったとしても、それは最初の1個が特別であるのと同じように、その形状や香り、精妙な粒その1つ1つに驚きを見出すことができる。古典に通暁しながら、しなやかに〈今〉を作る。そんな作曲家の庭で採れたオレンジ=作品は、新鮮な煌めきと知的な喜びに溢れている。

ダニエル・ウォールは、パリで生まれ育ち、現在はLAに住む電子音響(エレクトロ・アコースティック)の作曲家だ。イェール大学作曲科の博士課程を修了、作曲と映像音響の先達デヴィッド・ラングらに学び、最晩年のヨハン・ヨハンソンともコラボを経験したことも大きいのだろう。ドビュッシーに始まり、メシアン、ライヒ、クセナキスに影響を受けたクラシックの作曲家と電子音楽家の双方の視点を持ちながら、音の色彩感覚や音質の探求を何よりも重視する。アトモスフェリックなドローンに、プロセッシングされた生楽器の録音やデジタルなシンセ音、ノイズ音などが、作曲面ミクシング面双方において有機的に絡み合い、独特のシネマティックな音響を生み出す。例えば、音色という単一の要素で見れば、今までもドローンやアンビエント音楽などで、それに近い感覚を与えてくれるアーティストがいた。しかし、音色作りから作曲し始める彼は、ミニマリスティックに限定せず、それに対位法のように相対する複数の音色やテクスチャーの選択を自分に課し、フレーズやメロディなど、ピッチ選択のアイディアも豊富。展開も多彩で、没入していく感覚に驚嘆すべき多層性が加わる。今回のフランス語で〈状態〉を意味する『État』は、インディー・クラシックで知られたチャンバーグループ〈yMusic〉のメンバー、ポスト・クラシカルの代表的な存在のダスティン・オハロラン、インディーロックバンド、サン・ラックスのライアン・ロット、またポリサのチェニー・レナ(Channy Leaneagh)が参加している。「出来うる限り深い音作りを追求したい」と語る彼だが、作品における深さが、参加する個性の生かし方からもまた伺える力作になっている。

ウィリアム・ブリッテルは、ニュー・アムステルダムの共同創立者であり、共同アーティスティック・ディレクターの顔を持ち、クラシックやジャズのみならず、パンクバンド、テレヴィジョンのギタリスト、リチャード・ロイドの自由なパンク精神に大きな影響を受けたバックグラウンドを持つ。やがてアカデミックな場所からドロップアウトし自身もパンクバンドを率いるも、不幸にも喉を壊して以降は、ローアー・デンズ、ワイ・オーク、サン・ラックスからワンオートリックス・ポイント・ネヴァーに到るまでのアレンジも行なってきた。彼の新作『Spiritual America』は、多ジャンルの音楽言語が内包されており(本人は流動するジャンル性genre-fluidと称する)、ワイ・オークのジェン・ワズナーを前面に女性ヴォーカリストとして迎えた、黙示録的で耽美的なSFのような作品になっている。プリンスの影響を感じさせつつ、電子的にエディットされ重ね合わされたヴォーカルとコーラス、ホーンやストリングのオーケストラアレンジ、エレクトリックギター、80年代的なフューチャリスティックなベースが絡み合う。ボン・イヴェール作品も手がけるザック・ハンソンによるミキシングもあり、現代ポップ的な洗練を持つ。曲全体においては各楽器パートが自由に構造を飛び出し、互いに独立して対話しながら、しかしそこには確実に作曲の構成が立ち上がるような、今までになかったような、流動していく音楽の醍醐味を味わえる。
先日web上の英語インタヴューで、インディー・クラシックという言葉はあくまでレーベルの一部分を示すに過ぎず、もはやその現実を示さないと告げた。満を持して発表された3つの作品は、ジャンルが全く異なるようでいて、従来の形式や構造に対して、深いところでクリティカルな面を持っていることでは共通し、このレーベルの新しいクリエイションの形を予兆させる。画期的な共同リリースは来年も続くと言う。アーティスト3人の今後はもちろん、レーベルの動向も刮目して見守りたい。
(text: 大西穣)