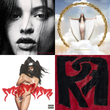天野龍太郎「Mikiki編集部の田中と天野が海外シーンで発表された楽曲から必聴の5曲を紹介する週刊連載〈Pop Style Now〉。この一週間の話題といえば、〈Camp Flog Gnaw〉でのドレイク・大ブーイング事件でしょうか」
田中亮太「タイラー・ザ・クリエイターが主催するフェスの大トリとしてドレイクが出演したんですよね。告知の段階で〈シークレット・ゲスト〉とされていて、なぜか多くの人が〈フランク・オーシャンらしい……〉と噂していたなかでの登場だったんです。それで〈ドレイクかよー〉とみんなガッカリしたみたいで。かわいそう……」
天野「この件、ドレイクはなにも悪くないですからね……。ライヴも20分で切り上げて退場したようです。SNSで炎上させて何かを中止に追い込むなど、こういう事件は最近〈キャンセル・カルチャー〉と呼ばれていて、欧米では大問題になっています。とはいえ、転んでもタダでは起きないのもドレイク。終演後にインスタでタイラーとの写真と〈Camp Flog Gnawと10年契約を結んだぜ、毎年会おう!〉というコメントをアップしました」
田中「これはナイスな切り返し。ドレイク、やるじゃん。それでは、今週のプレイリストと〈Song Of The Week〉から!」
1. ROSALÍA “A Palé”
Song Of The Week
天野「〈SOTW〉はロザリアの“A Palé”です! ロザリアはたぶん、〈PSN〉最多選出アーティストなんじゃないかなって思います。3月の“Con Altura”、6月の“Aute Cuture”、7月の“Fucking Money Man”、そしてこの新曲と4回目です。すごい!」
田中「というわけで、熱心な読者の方であればご説明不要かと思いますが、スペイン出身のロザリアはネオ・フラメンコ/アーバン・フラメンコを象徴する若きスターです。伝統的なフラメンコの音楽性を拡張したポップスとスペイン語の歌で世界を席巻中。本当に、2019年を代表する音楽家ですよね」
天野「ポップスターとしての存在感はもちろん、楽曲のすばらしさに毎回うならされています。この“A Palé”も強烈。いかにもフラメンコっぽいメロディーを繊細に歌うイントロに、いきなり〈ぶーん〉って鳴るサブ・ベースがぶっこまれて、一気にコンテンポラリーなサウンドになるんです。こういう音、英語圏では〈ベースヘヴィー(bass-heavy)〉ってよく表現されますね。〈A palé, a palé..〉と繰り返すサビでは、左右のチャンネルで歪みまくったパーカッションのような音が鳴っていて、こわいくらい。不穏なアウトロでは壊れたトラップみたいなサウンドが数秒間鳴り響くんですけど、それがめちゃくちゃ不穏。ほとんどサブ・ベースとパーカッション、ロザリアのヴォーカル、切り刻まれたヴォイス・サンプルだけで構成されていて、ものすごく緊張感があります。ポップ・ミュージックの最先端を感じますね。プログレッシヴ!」
田中「楽曲を手掛けたのは、これまでの曲にも関わっていたエル・グインチョ。そしてカナダのプロデューサー/DJであるフランク・デュークスです。テイラー・スウィフトやポスト・マローン、ウィークエンドなど、ポップ界の最前線をいくアーティストたちの楽曲を手掛ける売れっ子ですね。それにしても、昨年の傑作『El Mal Querer』に続くロザリアの新作はいつ発表されるんでしょうね? 待ち遠しいです!」
2. Best Coast “For The First Time”
田中「2位はカリフォルニアの男女サーフ・ポップ・デュオ、ベスト・コーストの新曲“For The First Time”。この曲の発表に合わせて、2020年にニュー・アルバム『Always Tomorrow』をリリースすることも決定。彼らは昨年、子ども向けのカヴァー盤『Best Kids』をAmazon限定でリリースしていたんですが、オリジナル・アルバムとしては2015年の『California Nights』以来の新作。ちょっとお久しぶりな感じがありましたね」
天野「亮太さんは〈サーフ・ポップ・デュオ〉なんて決まり文句で紹介されましたけど、この曲、もはやサーフ・ポップでもなんでもないじゃないですか(笑)! ベスト・コーストはどんどん80sポップ~AOR化している印象で、なんかノれないんですよね……。西海岸でヨット・ロックが大流行中なのはわかるんですけど、単純な懐古趣味にはあんまり興味がないので」
田中「えー、僕は彼らのこの路線、最高に好きですけどね。この“For The First Time”は、ビーチ・ボーイズの“Kokomo”(88年)みたいじゃないですか。ポコポコとした可愛らしいリズムとか、オールティーズ調のおセンチなメロディーとか。加えて、ライトニング・シーズあたりのセカンド・サマー・オブ・ラヴ期のバレアリックなポップスに近い雰囲気も堪らないです」
天野「後ろ向きすぎる! まあ、インディーなサウンドから、より大衆的な歌を志向していく姿勢は、キャリアの重ね方として悪くはないと思いますけどね。今日みたいな金曜日の夜、疲れた身体に〈ごくろうさま〉とバーでビールを流し込む。そんな風景が脳裏に浮かぶ一曲でした。じゃあ、僕たちも飲みに行きますか!」
3. MC Kevin o Chris feat. Drake “Ela é do tipo (Remix)”
田中「残念ながらまだ飲みには行きません……。気を取り直して3位は先日、不幸なブーイング攻撃を浴びたドレイクが参加した、MCケヴィン・O・クリスの“Ela é do tipo”リミックス・ヴァージョン。オルゴール調の音を使ったドリーミーなウワモノと、潰れた音のハードなビートが明らかにアンバランス。なのに不思議な中毒性があって、おもしろい曲ですね。このMCケヴィン・O・クリスって人は誰なんですか?」
天野「彼はブラジルの人気MCですね。バイレ・ファンキ/ファンキ・カリオカのビートで歌うのを得意としているみたいで、なかでも〈ファンク150BPM〉という新興ジャンルの代表的なアーティストなんだとか。おもしろいですよね。音楽シーンでは常に新しいことが起きている!」
田中「なるほどー。ボン・ジ・デ・ホレも今は昔、バイレ・ファンキもいろいろ進化しているんですね」
天野「また懐かしい名前を出してきますね! この曲については、ドレイクがこういったビートで歌うことが意外で、そこが新鮮。リリースも彼のレーベル、OVOサウンドからですし、ケヴィン・O・クリスのことを気に入っているんでしょうね。なので、ドレイクの次作を占う視点と、なにより〈ドレイク、元気出して!〉という気持ちから選出しました(笑)!」
4. Mura Masa feat. slowhtai “Deal Wiv It”
天野「4位は、グラミー賞にもノミネートされ、エレクトロニック・ミュージック界を席巻するムラ・マサがラッパーのスロウタイをフィーチャーした“Deal Wiv It”。あんまり知られていないんですけど、ムラ・マサはイギリス海峡にあるガーンジー島生まれなんですよね。なんにもなさそうだけど、気候はすごくよさそう」
田中「そのムラ・マサ、日本でも大人気ですよね。名前が日本刀の〈村正〉に由来するからでしょうか? それともヒップホップからベース・ミュージックまで取り込んだ、折衷的な音楽性だからでしょうか? それはともかく、この新曲はヒット作『Mura Masa』(2017年)とはまったく異なるサウンドです。ぶっきらぼうなベースラインも、ギターのカッティングも、ダブ処理も、70年代末から80年代初頭のポスト・パンクそのもの」
天野「マジでそうですね。びっくりします。10月に出たシングル“No Hope Generation”もちょっとそれっぽかったんですけど、あれはもっとロックンロールっぽくて。曲名もすごいし、〈なんでいきなりこんな曲を出したんだろう?〉って不思議に思いました。で、今回はポスト・パンクと。スロウタイの煽るようなラップや声質もサウンドにぴったりですよね。でも、キックやスネア・ドラムが気持ちよく鳴る感じは、さすがの音作りだなって思いました」
田中「この後はどうなるんでしょうね? 2020年1月17日(金)にリリースされるニュー・アルバム『R.Y.C』、どんな作品になっているのか想像できません」
5. J Hus “Must Be”
天野「今週最後の一曲となりました。5位はJ・ハスの“Must Be”です。太いベースやサックス、クラシカルなストリングスなど、生音っぽいサウンド随所で活かされたクールなプロダクションがかっこいい」
田中「ガンビア系イギリス人のJ・ハスは現在のUKラップを代表するようなラッパーで、デビュー・アルバム『Common Sense』(2017年)はマーキュリー・プライズやブリット・アワードにノミネートされるなど、高い評価を受けました。アフロビーツやダンスホールなど、さまざまなサウンドを乗りこなす、すばらしい才能の持ち主です」
天野「この“Must Be”も明らかにダンスホール・レゲエっぽいですよね。プロデューサーは、『Common Sense』でも活躍していたJAE5です。実はJ・ハス、昨年6月にナイフを所持していた咎で捕まり、8か月の禁錮を言い渡されたんです。それで、ようやく刑務所から出てこられたのが今年4月。ひどいですよね。人種差別なんじゃないかって思っちゃうんですけど」
田中「だから音楽活動ができていなかったんですね。今年はドレイクのコンサートにサプライズで出演もしましが、ここにきてようやく新曲が届けられました。ファースト・ヴァースの冒頭は〈どうしようもなくなった男を見ていた/やつは閉じ込められていたんだ〉といった具合。歯切れのいいラップで、自分自身を客観的に描いているかのようにも感じます。J・ハスの帰還、今後の活躍も楽しみですね」