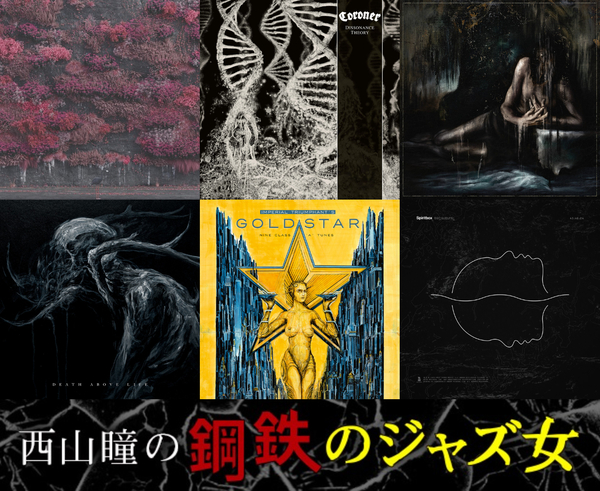③-1 新作『FIBS』に聴くクラシック~現代音楽のエレメント
クラシック~現代音楽では、作曲をしてそれを譜面に起こしたら、あとはプレイヤーに渡してアウトプットの最後まで責任が持てないというのが嫌だったとアンナ・メレディスは述べている。エレクトロニック・ミュージックに手を伸ばしたのは、最後まで自分の責任で完結できるからだそうだ。
そうして彼女はモシモシ・レコーズから2枚のEP『Black Prince Fury』『Jet Black Raider』(2013年)をリリースした。同作では、現在のようなクラシックの素養、バンド・サウンド、エレクトロニクスが混然一体となった折衷的なエクスペリメンタル・サウンドにはまだ結実していないが、最新作『FIBS』に至るまでの道筋はうっすらと見えているし、イレイジャー“A Little Respect”(88年)というシンセ・ポップ・ナンバーをカヴァーするなど、この段階でポップスへの接近も視野に入れていたことが窺える。
彼女の名を本格的に世界に知らしめることになったのはファースト・フル・アルバム『Varmints』だ。EPよりも洗練され、音がヴァラエティーに富み、自身の音楽的なヴォキャブラリーを磨きぬいたうえで整理した本作には、新作『FIBS』にも引き継がれることになるバンド・メンバーのサム・ウィルソン(ドラムス/パーカッション)やジャック・ロス(ギター)に加え、ジェマ・コスト(チェロ)や、レディオヘッドとも仕事をし、現代のクラシック・シーンを牽引するオリヴァー・コーツ(チェロ)なども参加している。
同作はスコットランドの国民的音楽賞であるスコティッシュ・アルバム・オブ・ザ・イヤー・アウォードで最優秀賞での受賞をはじめ、様々な音楽メディアで称賛された。『FIBS』は、そんな『Varmints』を音楽的な方向性を変えないままブラッシュアップした作品といえるだろう。
『FIBS』からは『Varmints』と同様に、クラシック~現代音楽の特徴が見いだせる。すぐに気づけるところとしては、“Bump”ではホーン、“moonmoons”ではストリングスのリフレインを楽曲の中央に据えて打楽器やエレクトロニクスとの連携に用いている点だ。
また、実際にそういった生楽器を使用しているだけではなく、“Calion”の中盤からビートに柔らかに覆いかぶさってゆき楽曲のムードを作る、たなびくようなシンセは、まるでストリングスがグリッサンドしているような動きをする(これは“Dividing”などでも聴ける)などもそうだ。
ミュージカルやオペラなどで耳にするようなどこか大仰なメロディーの存在も当てはまるだろう。特に“Sawbones”の冒頭の、チェンバロのような音色のシンセとギターのカッティングがリフレインし、それに続いて徐々にシンセの音高が上昇してゆく箇所などはそれにあたる。
そのほかにも特に意識しているわけではなくどこか染み出てきているような点が多々あり、そこかしこに見られるクラシック~現代音楽のフレイヴァーは彼女の音楽の魅力の大きな要素だ。
③-2 ブライトでエレガントな『FIBS』のシンセ・ポップ
ブライトで、かつエレガントなシンセ・ポップの存在は『FIBS』でもじつに輝かしい成果を見せている。煌びやかなシンセの音色や、展開の多いアレンジメントはもちろん、自分はいわゆるシンガー・タイプのヴォーカリストではないと述べるアンナ・メレディスのヴォーカル・アレンジが見事だ。
“Inhale Exhale”では途中でヴォーカルを左右のチャンネルに振り分けると同時にトラックに変化をつけることで音の自由度を広げることに成功しているし、彼女の素直なヴォーカルが聴ける“Ribbons”や“Unfurl”では、けっしてトラックに重心を寄せたりするでもなく、ヴォーカルにエフェクトをかけたりするでもなく、素材としての自身の声の取り扱いを熟知したうえでサウンドを組み立てており、魅力的な歌モノにしている。“Killjoy”や“Dividing”では男女の混声コーラスが的確に配置され、生楽器やエレクトロニクスと絡み合うようにして楽曲に格調高いフックを与えており、この辺りもさすがというほかない。
『FIBS』の白眉は、なによりも“Paramour”だろう。様々な音色が、精密に組み立てられた細やかなリフレインのもとでモジュールを形成し、それが連結することで圧倒的なダイナミズムをもたらす。中心となる音色はその時々でどんどん変化してゆき、これほどまでに色鮮やかなアイデアが溢れているヴァリエーションを生み出したアンナ・メレディスの作曲能力に驚かされる。
とはいえ、本作の難点をすこしばかり述べておくならば、“Limpet”などに象徴されるようにギターとドラムの音色/音響に工夫が足りない部分が耳につくところだろう。昨今のバンド・サウンドの風潮からしても、この点への意識の欠落はクリティカルだ。次作以降で改善されることを願う。
強烈な〈個〉こそが、音楽のボーダーを越境する
アンナ・メレディスのキャリアとサウンドを理解することは、現在様々なところで言われているクラシック~現代音楽の作曲家の越境性について理解することにも繋がってくるのではないか。そのような想いに駆られ、3つのアングルから彼女を照らし出した。
彼女はポスト・クラシカルにもインディー・クラシックにも、それに類する何かしらのシーンに属する音楽家ではない。ある種の集団性をバックグラウンドに持たない強烈な〈個〉だ。しかし〈個〉であるからこそ、思いもよらぬところにアクセスしうるだろうし、そういったある種デタラメで無軌道にも見える音楽家の存在こそが、クラシック~現代音楽の作曲家の越境性が、一過性ではない時代の空気の息吹を、確かなものとしてぼくたちに感じさせる。