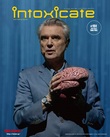勝手な思い込みで食わず嫌いになってしまうのはもったいない
マッコイの1960年代前半の演奏を聴くと基本に忠実であることに驚く。先ほどの『Night Of Ballads & Blues』にしてもコルトレーンの『Ballad』にしても、ペダル最小限で単音を生かしたホーンライクな演奏をし、バリー・ハリス氏も提唱する6thコードやディミニッシュ(減三和音)を使った音の動かし方を習得・実践している。まあ当たり前失礼千万な話だ。あの時代にニューヨークの第一線で活躍し注目を浴びていた人。そんな中にも特有の〈ペンタトニック・スケール(五音音階)ずらし〉アプローチが見え隠れしているのが興味深いのだが。
それが60年代後期、コルトレーンの『A Love Supreme』(65年)ソロの『The Real McCoy』(67年)頃からのスタイルを見ると、〈ペンタトニックずらしテクニック〉が際立ってゆく。II-V-Iといった頻繁に出てくるコード進行上でも、構成音にきっちり沿うのではなく、4つほどの音型を繰り返したり音域を変えることで、メカニカルな構造美が生じる。コード進行感をそぎ落としたコルトレーンやエルヴィン・ジョーンズの怒濤のサウンドの中で埋もれず音の存在感を出してゆく過程で編み出された奏法なのかもしれない。それゆえにマッコイのピアノは表面的には真似しやすい。例えば左手で下から〈ファ・シ・ミ(4度和音)〉と同時におさえ、右手で〈ミシレソミレシ〉と弾いてみよう。似たようなことを黒鍵だけでもやる。ほらもうそれっぽくなるでしょ? マッコイの場合これをあらゆるキーで習得した上で自由自在にずらしてアプローチするわけで、なかなかこれに徹する(つまり半音だとか間の音を出さないように)のは並大抵のことではないのだけれど。もちろん良く聞くとm7系のペンタトニックだけでなく7thやm6の構成音も使っていて……おっと楽理の話はこれくらいにしておくが、この奏法を生み出し確立したのがマッコイの大きな功績であることは間違いない。
このようなスタイルの変化について、画家ジャクソン・ポロックが初期~中期頃までは具象画や対象の見える絵を描いていたが、晩年になってドロッピングに徹するようになってから個性が確立したのと同様に感じる。