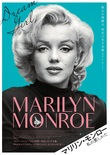4
もし「ノットゥルノ」に二つヴァージョンがあるとしたらどうだろう。これがあり、そしてそれから完全な改造、セットと俳優たちを使ってクレジット以外は区別することができない作品を作る。そんなヴァージョンは違った影響を及ぼすだろうか? 例えば〈出演:Samira al Haqq(役:Neda Hosseiniの母)〉といったクレジットを読んだ後で、私たちの見方はどれくらい違うのだろう? もし息子の殺害を嘆き悲しむ女性は、女優が演じているのだと知ったとしたらその効果はどう違うだろう。フィクション、あるいはドキュメンタリーの分類もまた、〈実際の出来事に基づく〉というよく目にする表示のように予め仕込まれている形式なのである。
「ノットゥルノ」に沿ってこの疑問をさらに追求すると、ある興味深い可能性が生じる。つまり、もし「ノットゥルノ」が実際にフィクションだった場合、映画制作の語り口のルールをたくさん犯しているので、不備があり役に立たないと、批判されるだろう。第一に、はっきりとした展開がない。ほとんどの登場人物は再登場しないし、そのほとんどは喋り声すら聞こえない。追うべき主人公もいない。私たちは、誰かの内に秘めた考えや意見を知ることはない。それぞれのシーン、あるいはいずれかの登場人物が、あるシーンから次へとどのように関係付けられているのか明らかではない。寓話性から非現実性へ、臨床的なものから平凡なものへと至るシーン(見た目)の在り様の移り変わりは、フィクション映画としては、文体的に支離滅裂とみなされるだろう。それでいて、この変則的な組み立てられ方は、繋ぎ目がなく、十分に首尾一貫していると感じる。「ノットゥルノ」のシークェンスに論理的流れを見出すことは不可能だが、その構築性と完結性には、異常なほどの生々しい力がある。
ロージは以前、ドキュメンタリーとフィクションの境界で制作していて、事実、二度ドキュメンタリーで最優秀賞に輝いた唯一の映画監督だろう。最初が「Sacro GRA」、そして「Fire at Sea」である。「Sacro GRA」での、見え方、進み方、そして展開はとても美学的に洗練されており、その三つの自然な生起は信じ難く、それが人気映画のシーンだったなら、非常にうまくデザインされ、撮影され演じられたと賞賛されていただろう。しかしその映画は、ある場所の住民の肖像として構成されていて、このアプローチは相応しく、容易に受け入れられた。「ノットゥルノ」では、テーマはより複雑で曖昧だ。実際に、ロージ氏が撮影を始めた時、テーマが何なのか、全くはっきりしていなかった。彼が引きつけられたのは、政治的かつ宗教的に厄介な火薬庫で、改善すればするほどますます悪化するというその地域の評判だった。テーマとして魅力的なのは、遍く誤解された場所というよりは、ドキュメンタリーだった。
しかし、「ノットゥルノ」がドキュメンタリーであるのか、フィクションなのかという考察は重要ではない。もしフィクション映画だとすれば、メディアの全ての要素に対し過激なほど自由で大胆なアプローチが採用された。そして事実、フィクション映画が掻いた痒みを引っ掻いた。雰囲気、謎、エキゾティシズム、水々しいヴィジュアル、催眠術のようなリズム。しかし、もっと驚異的なのだ。物語が要求する妥当性に縛れらていない。「ノットゥルノ」に集められた本質的に異なる要素の連続は、氷の結晶化や溶岩の冷却のような、自然のプロセスの不変の正確さで進む。捉えられたのは、観衆が適合するものを見て、合わないものは看過するように仕向ける、物語の領域や物語の還元主義を超えた何かだ。部分が自由なままなのは、シークェンスにおけるその機能が決して明かではないからだ。なぜなら部分は増加するのではなく、増殖するのだから。観衆はこの世界が何なのかとか、どう機能しているのかを始終理解しようとする事実、つまり映画の思考、願うことならば洞察を刺激する能力が、最後のショットにまで続く。逆説的に、出来上がったトーンの範囲や行われた実験はフィクション、明らかに商業的フィクションの許容範囲を超えている。あなたは、「ノットゥルノ」を、フィクションのようだが、ドキュメンタリーの権威があると言うかもしれない。そしてその権威はその代わりに形式的自由を制限する。
5
嘆く母親のシーンに若い男がバイクでハイウェイを飛ばすショットが続く。景観の唯一の特徴が水平線の遥か向こうに現れる。油田の二つの炎だ。この男は戦争の現実とは無関係である。彼は銃を持っているが、それは狩猟用のライフルだ。湿地に茂る葦に隠した小さなボートを見つけると、遮るもののない水域へと漕ぎ出し、囮りを投げて、上空のカモへと目配せしながら漂う。彼の映像は、この前のシーンの残酷さを柔らげる感情や、路上の喜びや気楽さの、この映画の他では感じられない何気ない生活の自由な感覚さえ即座に生む。草深い水辺に玩具のボートのように浮かぶ囮りが、この感情を引き立たせる。カモを狩るハンターがシーンの終わりに再び現れるとき、その安堵感の必要性は増すが、彼の役割は変わらない。囮りは以前よりさらに意味ありげに見える。囮りはまるで、シンボル、しくじりのシンボルのように際立つ。囮りは一羽のカモすらおびき寄せない。囮りは映画に起こる、繰り返される置き換えと二重化を思い出させる。水道管のゴボゴボという音、機関銃の銃声、広大で空っぽの土地を護る兵士たちが見つめる戦いの映像、子供たちが描く残虐行為、トラウマとなった出来事を演じる患者たち。そして今、もう一つの奇妙で説得力のある二重化の映像が、オレンジの空の水平線、その遥か遠くに、まるで二つの太陽のように並んで、脈打つようにどんどん強烈に燃え上がりながら、オレンジに水面全体を反射して、現れる。二つの太陽は川を滑るようにハンターが横切るのを尾行しているように見える。それは二つの遠い油田のガスの炎だ。この二つの太陽というアイデアには、相応しい何かが、想像し得るであろう限りに強力で、不自然な兆しがある。
彼の役割は解放をもたらすことなのか? 彼が二度登場するという事実は、映画において重要な役だと考えられていることを示しているだろう、彼は喋らないし、ほかのどんな登場人物とも無関係なのだが。私たちが知っているのは、彼が狩をして、オートバイを持っているということだけだ。彼に移入するほどではないが、私たちは彼と共に感じているのかもしれない。そしてこれが、「ノットゥルノ」のアプローチを理解する手がかりなのかもしれない。ほとんどの登場人物は沈黙している。彼らを見てはいるが、聞くことはないし、彼らが何を考えているのか知らない。ハンターのシーンは、「ノットゥルノ」に本質的なパラドックスを際立たせる。物語も中心的人物もいないが、それは結びつき、高まっていく。
もう一つ同じように素晴らしく、しかしその機能は謎めいていて映画の中心に自由に漂うようなシーンがある。夜の車が行き交う交差点の真ん中に立っている馬だ。ほんの5秒程度(それでもすでに今の映画なら長い)だったなら、興味深い細部でありそれ以上のことだったかもしれないが、しかしシーンはたっぷり50秒続く。最初、そのショットはその場所での街の生活の様子を垣間見せようとしたように思えるが、それは続く。馬は時折、通り過ぎる乗り物のヘッドライトに照らされて、フレームの中央で、カメラをまっすぐ見つめている。それは馬だけに許された時間。馬は私たちを直視して、その効果は驚くべきもので、敵意を萎ませる効果をもたらす。馬は異質であるだけでなく奇妙で、馬自身の基準で変質したこの世界を覗き込む部外者、私たちの認証者、観衆の代理人を務めている。私たちのようには話すことができない馬は場違いで、周囲は車が行き交い、無関心に、頑なに、私たちを見返し続ける。したがって、観衆との最も明快な同一化、あるいは鏡像かもしれないその接触感の強烈な実例を、カメラに目も向けず、考えをほとんど表現しない人間よりも、もたらしているのは動物なのだ。時に馬もまた古代の存在だ。地域に生息し、軍用の乗り物で戦車や車が発明されるずいぶん前からの交通手段だ。だから、馬は部外者であり、祖先、そして監督がある会話で言い表したように、神託なのだ。
もう一つ、異常に引き伸ばされているシーンが、映画の後半に登場して、同じ不安を産む。まるで浅瀬を削る船、停止することなく、沈んだ物体にただぶつかりながらながら進み続ける。底があるという警鐘の効果だ。アート・セラピストとのセッション中の少女は、ISIS占領下での彼女のおぞましい経験を描写している。患者の中でもひどいトラウマを病んだ彼女は、机上に伏せた頭を横にした状態で話す。彼女は子供が泣いた時、兵士たちがどんなふうに殴るのかを描写する。「これが子供達の血」。机上の彼女の絵にある赤い染みのことを話す。セラピストは振り返って彼女を見ると、34秒間たっぷり、何も言わない。これは彼女が泣き崩れるまでその姿にずっと釘付けになる、よくある「お金のかかったショット」ではない。少女とセラピストの二人はじっと沈黙のままだが、この沈黙の中で何かが起こる。彼女が描写する子供たちの恐怖にセラピストは圧倒されたのか? 彼女自身の恐怖心に? あるいはセラピストは何か全く別なことを考えているのだろうか、もっと些末な何かを? これは「口に出せないこと」の認知なのか? それともカメラのせいで、話したり、行うことが彼女にはできない何かがあるのか? この異常な瞬間に、映画はあらゆる可能性、映画が行き詰まらせた可能性、あるいは失敗してここで終わってしまうという可能性に向けて開く。
あたかもこの時、映画は穴だらけのようだ。それは俳優が舞台上で台詞を忘れて固まっているその時に演技のリアリテイと劇の策略が剥き出しにされて、スペクタクルの支配が疑問に伏される、そんな瞬間のようだ。そんなところでは、誰もが舞台に上がって、乗っ取ることができる。映画では、ある強力な効果をあげるのは、可能性ではなくて、馬のシーンのような瞬間が導入する突然の不安定性なのだ。演劇とは対照的に(少なくともそういう経験のある監督の)映画において、それは考え抜かれたこととして理解されるか、あるいは編集で消されてしまうのだが。
しかしもしこれらの瞬間が底を削る船だとして、底とは何なのか?
「夢解釈」の中で、フロイトは、全ての夢には素材が手がつけられないほど込み入って絡まり、解釈不能の場所があると述べている。彼はそれを夢の「臍の尾で、不可知なものへと達する場所」だと言及している。それは不可知なものへの導管だが、無感覚で、密封された、それもまた起源である障壁なのだ。こうした考えが含意することや、さらに良いことには、これらの自己矛盾が、「ノットゥルノ」の魅力的なレンズを作り出す。これらの、すでに描写された〈停止〉の瞬間は、映画の全てが、実際のドキュメンタリーの映像、つまり〈リアル・ライフ〉なのだという事実にもかかわらず、解釈されたり、理解されたりすることができない素材を含んでいるということを提示する。
もし実際に「ノットゥルノ」が、可知と不可知の両方を含んでいるのだとしても、どちらがどちらかなのかが示されない。その凝視は、絶対的に不変で、とはいうものの同時に厳格な形式で、イメージの表現において断固としている。不安定な素材の混合物へのフォーカスの高度な確実性である。
この映画か夢かにかかわらず、この底あるいは臍の尾が媒体の限界、コミュニケーションの限界、表現そのものだろう。フィクションというよりドキュメンタリー形式、美学よりは認識論にとってこれは興味深い問題である。他者の観察を通じて何を理解するのか? 我々が前提とし、慣れている理解の形式とは何か? そして別な理解の仕方とはなんだろうか?
夢への参照は、意識と無意識の区別に関する疑問を導入する、そしてそれが回答不能の疑問だとすれば魅力的なのである。映画は無意識をとらえることができるのか、もしそうであれば、無意識は何に似ているだろう? 無意識の力によって引き起こされる、チックや爆発性障害のような行動とは対照的に、この世界の無意識を捉えたと言い得るパッセージがこの映画にはあるのか。一体も通過しない非現実的な検問所、虚な歩哨、溢れて壊れている道路の車の流れ、夜、人気のない街路を走る馬?
監督による示唆や注釈の不在は、対象者たち、すでに記した通り彼らの考えを私たちは単に知らないのだが、彼らの会話の欠如と混ぜ合わされる。「ノットゥルノ」が提示する唯一明快な情報は、アート・セラピストのトラウマを抱えた子供の患者たち、もしくはトラウマを負った精神病の患者たちから提供される。良きことから悪しきことを分ける、今日の世界が慣れて、押し付ける決定的瞬間は、留保されている。映画は素材のタイプを分けたり、あるいは秩序づけることはしない。映画は無意識しか撮影していないとさえ言えるだろうし、そしてこのことが表現の固有のモードを説明する。役に立つ概念よりはずいぶんキャッチーだが。
これまでの議論の多くにさらに不穏なフォーカスをもたらすもう一つのシーンがある。精神病院の廊下で、明らかに障害のある患者が一足一足と、壁を背にして揺れ動いている。そしてその一方で、右側に向かって、南京錠がかかった二つの二重扉のわずかな隙間から断続的に見える、人が見ていて、火のついたタバコの赤が明滅するたびにこのわずかな隙間に顔が現れたり消えたりしている。その第二の男は誰だ?
監督は、以前登場したその患者を撮影したことに気がついていたのだろうか? どうしてこの扉は錠がかかっているのか? 彼らの背後にあるのは何なのか? 他の症状の患者の隔離区画なのだろうか? それとも完全に別の施設? 大統領の宮殿? 刑務所? それはこの世界に隠された別世界への一瞥。そして私たちはそれをたった数秒間目撃し、二度と見ることはない。これは臍の緒そのもの、私たちが決して知ることができないこと、観衆への映画の自律性の限界の警告、落とし戸、不可知の水位だ。

6
最初の二つのシーンで始まった戦争というテーマは、文学やアートでは広範囲にわたり探求されてきた唯一のテーマへと向かう。愛だ。夕暮れ、屋上の男と女。女は水タバコを吸っている。二人は深く結ばれている。彼女の吸う水タバコの泡立つ音が聞こえるが、もう一つ聞こえてくる音がある。遠くのマシンガンの銃声である。一つの音をもう一つの音と区別しようとして目を凝らすと、ふとある時、女の水パイプがその両方の音を発しているように思える。滑稽だが、おそらく、これが武器の音の起源であり、戦争の音の起源でさえあり、恋人との戯れのために、この二つを作ったのはこの恋に落ちた女性だという考えが導き出される。この考えは、偶然のこの音の配置から自然に生まれた。それはシュールだが、同時にもっともらしい。そしてこの暗示、このトリックによって、最初の二つのシーンで垣間見た戦争の残酷な現実は、難なく変容する。戦争のおぞましい真実は立証されて、そして消される。
この三つのシーンの三角法は、興味深い。兵士の行進、武装準備。悲しみにくれる戦死した兵士の母たち。もしかしたら単なる幻想だとして戦争の現実を見失わせる、男女の出会い。それぞれを支配するのは、転置の論理だ。実際のテーマである、戦争とカリフの統治は映らない。そして事実、「ノットゥルノ」全体の中で、唯一の戦いの映像は、携帯電話で見せられる動画、あるいは患者のために精神病院の医者が用意したメドレーなのだ。唯一私たちが目撃する発砲は、鳥に向けて撃ったハンターのもの。
映画が進むに従って、一層執拗に繰り返されるある疑問を提起して終わりに向かうシーンでは、この転置はより一層顕著になる。私たちは、市街のある場所の廃墟を見る。なんとか名残を保ったビルの、人気のない街路にばら撒かれた瓦礫、膨らんだ壁、窪んだ屋根、窓や扉のようなものはどこにもない。避難や救護ができるような場所もない(これも、変容の形式だ)。この風景の映像の向こうから、女性の声が聞こえる。それは、ISISに娘を捕らえられた母親が聞いている携帯の伝言メッセージの録音である。やがて明らかになるのは、その事実の後、百回、あるいは千回とずっと再生されているということ。これはおそらく、母が手にした娘の残したものの全てなのだろう。「もしお母さんと連絡をとっていることをISISが知れば、私は殺される」という最後のメッセージが暗示するように。残されたこの現在に存在はない。それは時と場所の完全な排除、不在の終わりなき繰り返しである。声そのものが不在の印であり、瓦礫がかつてここに栄えた都市の不在を記すように。そしてそれは記憶に留めて置くべきもう一つのこと、つまり戦争における女性の役割、生を与え、悲しむ、不在の印となった女性たち自身である。
7
水タバコによって変容した戦争のテーマにもう一つの偏光が続く。次のシーンは、夕暮れ時、間に合わせのバラックへと帰る、無言の、武器と用具を持った女性兵士の隊列を写す。彼女たちはどこにいる? 前線? もし戦闘があるのなら、戦場は遠いはずだ、というのもこのシーンは全くの無音だから。女性たちはブーツを脱いで、順に膝をついてお茶を立てるのにも使う灯油のヒーターを囲む。彼女たちはヘルメットを脱いで、薄暗い光の中、二列に並んで、長い髪を頭上へとなびかせ始める。それはあたかもダンスのようだ。エレガントで、的確な、儀式的だが無駄のない、女性の最も元型的な仕草の一つである髪の手入れをする。6、7本の手が同時に、無言のまま、螺旋状に動くのだ。彼女たちは全員が疲労を纏い、銃に寄り添って疲労に潜って眠る。彼女たちは誰? 手がかりは何もない。現役の兵士だが、唯一の戦いの映像を写すのは、彼女たちの携帯。朝になると、彼女たちは駅に向かう、何もない世界の歩哨として、そして塁壁の高所から、武装して、一つとして生き物の動く気配のない広大な平原を監視する。
夕方になると、彼女たちは壕から武装した乗り物に乗って転がり出て、人里離れた屋敷を急襲する。あたかもSWATのチームのように、全くの無音の屋敷を探索して、武器を剥き出しにして部屋から部屋へと急ぐ。このシーンは、この映画に痛々しいまでに欠けているあること、つまり普通の生活を即座に喚起する映画の中では唯一の短いシーンとなる。私たちが目にするのは、大きな二階建ての家、装飾された柱で縁取られた正面扉、カーテン付きの窓、立派な家具、高級木材家具、ベッドだ。全て以前の暴動で破壊され、照らしているのは兵士のライフルの先についた懐中電灯だけだが、それでもかつての生活の様子が映る。その孤立と原状回復の不可能性は、沈没船の探索を思わせる。そしてそれもまた、もう一つの不在のモニュメントなのだ。
女性兵士のシーンもまた、まるで非現実的な寓話のように思えるのだが。それはあたかもヴァレリオ・ズルリーニの「タタール人の砂漠」のように、それほど遠くないイランのバムでの撮影、過激に武装した前哨地、そこでは数十年ものあいだ目撃されていない敵である。彼女たちは、慎重に映画の残りとその地域のリアリティーへと編み込まれていくのだ。二人の兵士がISISがそこにまだ存在しているということについて語る、その交わしている言葉によって。
このシーンは、このテキストの最初に述べたように、この映画の組成と情報のコントロールのされ方に、極度に注意が払われたもう一つの例である。ヒーターを挟んでその両側に敷かれた簡易ベッドから、二人の兵士が言葉を交わすのだ。このシーンはさりげなくて、気が安まる。事実、その見た目を除けば、違う映画の一場面のように、さりげなく、気軽に感じる。一つには、この二人が登場するのはこのシーンが最初で、そしてこれが最後になるということ。第二に、恋人たちのシーンを除けば、本当の会話を耳にする、これが唯一の機会だということ。第三には、シーンはコミカルで、兵士の会話のパロディーのようでさえあるし、憂鬱な周囲の雰囲気を考えれば殊更に際立たせている。機銃掃射手が、マシンガンの常態的な使用からくる腰痛のことを愚痴っていること、道路の窪みに慎重なドライバーへの文句を言っていること。しかし、この明確に異なるシーンは、映画の他のシーンから注意深く切り離されている。シーンの後カメラが引くと、兵士のいる部屋が小さな灯に照らされた長方形となって、夜景が映るのである。兵士たちの会話が真剣味を帯びる。ISISがキルクークを攻撃したというのだ。そしてもし攻撃を止められなかったら、彼らが復活するだろうと。このちょっとしたシーンは、「ノットゥルノ」に、唯一、今日の政治の現実へと向かう具体的な方向性をもたらす。そして、これ以上は必要とされない。
8
この地域が耐えてきた残虐行為の二つの詳細な表現が、あらゆる論争とイデオロギーの軋轢を避けるような方法で現れる。一つ目は精神病院で、二つ目は子供たちとのアート・セラピーのセッションで。
精神病院のトラウマを抱えた患者たちが、おそらく彼らが病院に収容されることとなった政治的騒乱についての劇を演じている。劇は、監修もつとめる精神科医によって書かれた。台本を患者に手渡しながら、彼らの能力を維持するために書いたと、医師は患者に語る。偶然の政治的な注釈にしては、真実にしては出来過ぎだし、滑稽で、苦々しい皮肉だ。マルクスの定式では、歴史はまず最初に悲劇として、次に茶番として現れる。これは三番目の形式だ。言葉は辛辣で、首尾一貫しているし、ドキュメンタリーにおける注釈としては上手くいっているようだが、その効果はここでは逆だ。感情や活気がないのだから、紙の上では的を射ていた歴史的分析は、意味のない、悶々と混乱した状態になる。ただ医者だけが、演技を活気づけるために腕を振り、張り切っている。私たちはごく普通に字幕を読むことができるのにもかかわらず、それを分析することが不可能になる。その効果はパロディーであると同時に悲劇であり、不条理で不快で、まるでヴォネガットが現実化したようだ。
しかしこれは効果的なのか? 事実に関する何らかの識見や明晰さをもたらそうするのなら、これは失敗ではないか? 事実は依然として重要でなければならない。実際に、〈フェイク・ニュース〉や専門家への蔑視と言った、陰謀理論のこの時代に、事実はさらにもまして重要なのではないのか。「ノットゥルノ」は、因果関係や過失責任を立証しようとするもっと平凡なドキュメンタリーと比較して、知性や感情に違った働きかけをするが、ではどのような結果をもたらすのか? もしそのゴールが、問題についての考えや、当該地域や人々への態度を改めることだとすれば、答えは曖昧だ。ISIS統治の残虐行為に唖然とし、また再び残虐が起こらないことを求める人にとって、この映画は、より効果的なのだろうか? 映画は、形式的で美学的な戦略に囚われているのだろうか? それともこの戦略が、効果的なものなのか? 何故なら戦略は、思考のサブリミナルな活性化もたらすのだから。だが実際には、映画は、政治的な行動の流れを変えるようなどんな効果をこれまでに発揮したというのか? ポンテコロボの「アルジェの戦い」は? バーンズの「ベトナム戦争」は? グリフィスの「國民の創生」は? スターリンのプロパガンダは? 「チャンス」は? 「バンビ」は?
精神病院での歴史劇は、最近の出来事の映像をアラビアの歌に合わせて上映し、終わる。これらは、映画の中では実際の歴史的出来事の唯一のシーンで、映画では平凡なドキュメンタリーのように置かれている。奮起を促すシーンの連続、政治的な動揺や情熱、銅像の倒壊、砲火を浴びる建物、逃げ迷う人々――まさに歴史の核心だ。終わりにカメラは患者たち、聴衆の顔にズームインする。「ノットゥルノ」を観る私たちとの比較は不可避だ(もう一つの傷付いた底)。プロジェクターの揺らめく光に照らされて、歪んだ明暗法の、記念碑的な、トーテムのように、巨大な大理石のローマ人の頭のように顔が現れる。通常のドキュメンタリーでは、鑑賞している患者たちの目に涙を見るだろう。平凡なドキュメンタリーでは、患者の目にあるのは涙なのだろう。ここでは、しかし、映画の他のシーンでもあるように、人々の感情は、不可解で、近寄りがたい。居心地のよい世界ではお馴染みの、安易な情に訴える劇は、ここでは可能ではない。次から次へと顔のクローズアップ全てが、緊張した感情を期待し、欲しさえするように私たちを誘導するが、震える唇すらない。このシークェンスは最も厳格で赤裸々な、この場所での生活の描写なのかもしれない。シークェンスは、我々、そしてこのカメラには、手の届かない、知ることができないことなのだ。
こんなにも凝縮されたシーンに続いて何が映せるのだろう? その次のショットは、すやすやと眠る赤ん坊だ。この世界の重さ、偽りのない生活、あらゆる美と希望と、将来の展望を感じとるには若すぎる、赤ちゃん、未来、次の世代。
9
歴史の二度目の服用は、ISISの元での生活でトラウマを負った子供たちとのアート・セラピストのセッションに仕組まれている。彼らは、子供たちが経験した恐怖の絵について話している。学校によくあるようなやり方で彼らの作品は壁にテープで貼り付けられている。事実、これは、同時代の西側からそっくりそのままの、この映画では初のセットだ。新しい生徒の机と平服の教師の、モダンな教室だが、壁に貼られているのは、処刑、斬首、切断の絵で、その描き方は面白いが、その明快さと具体性にはゾッとする。語りは、怒りや憎悪を生み出すどころか、顕にもしない。表現されているのは、感情の未知の、雑多な前兆だ。吃りのひどい少年は一枚の写真を、ISISの指導者、アブー・バクル・アル=バグダーディーだと認めた。少年は彼を刑務所で見ていたのだ(バグダーディーは2019年10月に殺害された)。彼の語りは、吃りで耐えがたいほどに緊張する。説明することが困難な、驚くべき動きでだんだんと頭を片方へと傾下ながら、少年はずっとその写真を見つめている。ここでもだ、啓示的な静けさ、傷ついた底、魅惑的だが非感情的、まるで臨床的、そして解読不能。
それから次のシーン。広大で何もない刑務所の庭だ。門が開いて、ゆっくりと入ってくるのは、最初流れる花びらのように現れ、私たちが次に目にするのは、ついさっき描かれた残虐行為を犯した、まさにそのISISの兵士たちだが、今や解毒されて、姿を変え、オレンジ色のつなぎ服の男たちになっている。まるで個人の心理学ではなく、むしろ流体力学に支配されたプロセスの一部であるかのように、彼らはその空間に散らばって、混ざる。単なるオブジェのようなのだ。シーンは、私たちは、彼らが何をしたのかを知っているという事実にもかかわらず、美しい。焦げ茶色の色彩の建物と庭、苔緑の正門と守衛の制服、窓枠の底が蛇腹状になった鉄線で作られたハート型の輪。しかし、悲哀に、かき乱されるような、あるいは慰めるようなものは、このシーンにはない。あるのは数学的な、機械的な美しさだ。ショットが捉えるのは庭へ入ってくる囚人たちの入場の、はじめの一人から最後の一人まで入れた、その一部始終である。そこには法医学的な完全さと叙事詩的な緊張がある。収容者たちが、場所の隅々まで巡回し始めると、足首の真ん中までしかないつなぎ服と、全員が履く、大きすぎて、引きずっては跳ねるように歩くしかない、黒いフリップ・フロップが引き金となって、ある無関係なイメージがよぎる。彼らはまるで道化だ。茶番へと変容を遂げる悲劇である。
それから、彼らの運動時間が終わり独房へと巻き戻される。一列縦隊になって、無限に連なる繋がった昆虫のように、前の男の肩に手を置いて足をひきずるように。このシーンの全ては、無言で進む。これらのショットは、もう一つの変容をもたらす。口ごもる少年が描き、追体験した恐怖の、贖罪ではなく、むしろ代謝だ。人々を斬首し、子供たりに切断された頭を食べるよう命じたこの男たちは、個性を剥奪されて、ある有機体に包摂されて、自然の正義によって解毒されたのだ、地面に横たわる身体のように。彼らは、このシーンを遥かに超えて長く続き、そのずいぶん前に始まっていたプロセスの部分なのだ。それは、あたかも紙芝居のように、人間の行為、あるいは歴史のように、生まれついた、本来のスピードと頻度で、歪みなく、全て可視化され、その本来の居場所である多能性の中で初めて見られたかのごとく、捉えられたかのようだ。
その効果は、脱法ドラッグであるエクスタシーを服用させられて、トラウマとなった記憶を男女のセラピストに8時間以上にわたって支配される、PTSDを病むアメリカ人兵士たちのための、新たな実験的な治療を思わせる。そのプロセスは、患者たちにそのトラウマとなった出来事を遠くから眺め、トラウマを引き起こした経験との個人的なつながりを希釈し、和らげると言われている。彼らがしでかしたことでだけでなく、彼らに起こったことも、彼ら自身を許せると彼らが感じていると、多くの人は言う。