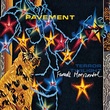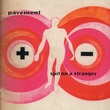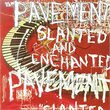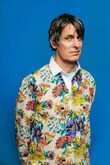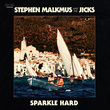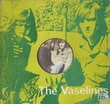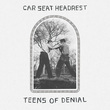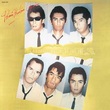家族のようなバンドにして独立独歩の存在、ヨ・ラ・テンゴとの対比
岡村「それと対比するわけでもないですけど、同じ時期にマタドールに所属していたヨ・ラ・テンゴとのキャリアの分岐がありますよね。そのヨ・ラ・テンゴは、この時代に非常に重要な作品を多く残し、その存在感を揺るぎないものにしました」
小熊「しかも、実験精神を忘れることなく、創作ペースをずっとキープしてますよね」
岡村「ええ。ヨ・ラ・テンゴって、人気が衰えないし駄作もないですし、メンバーは家族みたいな関係性ですけど、その当たり前の安定感に安住せず、常に新しいこともやりつづけて、ちゃんと成功しているバンドですよね。
これは穿った見方ですけど、当時レーベルのマタドールは、ペイヴメントにもそういう成長を期待していたのかな、という気もします。つまり、商業的な成功以外の付加価値や一味違うバンドになることを望んでいた、という」
小熊「それは面白い視点ですね。ヨ・ラ・テンゴを見ていると、独立独歩で続けることの大切さを痛感させられますから。ペイヴメントは、明らかにそういうバンドとはちがう」
――ヨ・ラ・テンゴとは対象的な、悪ガキどもって感じがしますね(笑)。
岡村「初来日のときは、まさに悪ガキどもでしたよ(笑)。
でも、最初からスティーヴンはちゃんとした美学を持ったミュージシャンという印象でした。だから、ヨ・ラ・テンゴと少し重なるようにも感じるんです。ヨ・ラ・テンゴには〈大人のバンド〉というイメージがあるけど、それはキャリアがそうさせているだけであって、彼ら自身は、心意気はずっとやんちゃなままなんですよ。独立独歩ではあっても、いつも時代にちゃんと沿った音作りをしている。奇跡的な存在とも言えますよね。ペイヴメントも、そうなっていく可能性があったと思います」
ブラーとの蜜月
――当時のペイヴメントといえば、ブラーに影響を与えた、というポイントもあります。
岡村「スティーヴンは、ブラーと仲が良かったですよね。ライナーノーツで〈スティーヴンはレコーディングでロンドンに行ったとき、エラスティカのジャスティーン・フリッシュマンのところに滞在していた〉とナイジェルが語っていて、〈ええっ〉と思いました(笑)。
当時のブラーは、特にギターのグレアム・コクソンがアメリカンオルタナからかなり影響を受けていて、ペイヴメントにものすごくシンパシーを感じていたようですね。そういう相思相愛の状況が、この時期にあったと」
小熊「ブラーの『13』がリリースされたのも、99年ですね。あれは、ある意味でペイヴメント的なサウンドの発展型だと思うんです」
エリオット・スミスと並ぶ影響力の鍵はソングライティング
小熊「そういうふうに当時のペイヴメントにはかなり影響力があったと思うんですけど、たぶん当時のシーンに与えた影響と、いまのシーンに与えている影響もだいぶ異なるのかなって」
――昔の音楽誌を読むと、ペイヴメントについては演奏のヘロヘロさの話が多いんですよね。一方、最近は、マルクマスのソングライティングが評価されることが多い印象です。
岡村「その点でいくと、90年代に活動して一定の評価を得たアーティストで、いまだに圧倒的な影響力を持っているアーティストといえば、ペイヴメントと並んでエリオット・スミスなんじゃないかと思うんです。その2組に共通するものが何かと言ったら、やっぱりソングライティングですよね。つまり、結局のところ、良い曲を書ける人だという、それに尽きるんです。『Terror Twilight』のリリースから20年以上経って、ペイヴメントが良い曲を書く人がいたバンドだと評価されるのは、すごく自然なことです」
小熊「エリオット・スミスの音楽が現代にも受け継がれているというのは、すごくわかります。実際、フランク・オーシャンから現代ジャズのミュージシャンまで、いろいろな人が彼からの影響を語っていたりするので。でも、R.E.M.やソニック・ユースよりもペイヴメントのほうが影響力を持っている未来は、きっと90年代には想像できなかったと思います」
岡村「そうですね。あと、エモの文脈も、プラスにはたらいているんじゃないでしょうか。彼がやっていたヒートマイザーがエモ的なバンドだったことが、いまの時代における、共振できるポイントになっているというか」
――それは、ジュリアン・ベイカーやフィービー・ブリジャーズのような現代のシンガーソングライターに通じる話ですよね。
岡村「本当にそうですね。『Terror Twilight』には、エモっぽさもありますから」
小熊「たしかに! いまの耳にはエモっぽく聞こえるかもしれない。ちなみに、ペイヴメントの曲でもダントツで再生回数が多いのは、“Harness Your Hopes”というこの時期のB面曲なんですよね。なぜかTikTokでバズったという。その辺も、エモや現代性の話と紐づけられそう。