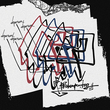ローファイの代表格として、90年代のUSオルタナティヴ・ロックに大きな足跡を残したペイヴメント。ひねくれた佇まい、醒めた視線、締まりのない演奏とグッド・メロディーは広く愛され、5枚のアルバムを残して99年に解散したあと、2010年にまさかの再結成ツアーも実現。当時の来日公演では若いオーディエンスの姿も目立ち、その影響力を再認識させられた。
中心人物のスティーヴン・マルクマスは、解散を機にソロ活動をスタート。自身のバンド=ジックスを率いて、ペイヴメントの音楽観を発展・拡張させるように7枚のアルバムを発表してきた。50代を過ぎたいまも創作意欲は衰えず、昨年リリースされた『Sparkle Hard』も健在ぶりをアピールする力作だった。
しかし、意表をつくように短いスパンで届けられた、ソロ名義としては18年ぶり(!)の新作『Groove Denied』は、なかなかの問題作に仕上がっている。Abletonを初めて導入し、マルクマス自身がシンセ、キーボード、ドラム・マシンなどを演奏した本作は、これまでのキャリアを覆すようなエレクトロニック・アルバム。先行公開された“Viktor Borgia”のミュージック・ビデオで、ポリゴン再現されたマルクマスがアリアナ・グランデに謎の勝負でKOされる一幕は、往年のファンを驚かせたに違いない。所属レーベルのマタドールが当初、本作のリリースを拒絶したという逸話もある。
このチャレンジングな一枚を、ペイヴメントの大ファンはどのように受け止めるのか? そこで今回は、髭の須藤寿、Homecomingsの畳野彩加と福富優樹、Helsinki Lambda Clubの橋本薫による座談会を企画。須藤が持参したスパークリング・ワインをたしなみながら、マルクマスの愛すべき魅力について、本家さながら緩くメロウに語り合った。

〈説明しづらい違和感〉を音楽で表現してくれたバンド
――まず、みなさんとペイヴメントとの出会いは?
須藤寿(髭)「僕がはじめて知ったのはサード・アルバムの『Wowee Zowee』(95年)じゃないかな。聴いてすぐに4作目の『Brighten The Corners』(97年)が出て、日本ではあのアルバムでパンと破裂したように人気が出た印象でしたね。『Brighten The Corners』からのシングル“Stereo”や“Shady Lane”といった曲で、みんながワオ!って感じになって。僕もその頃、〈BEAT UK〉でミュージック・ビデオを観て衝撃を受けました」
――須藤さんはリアルタイム世代なんですね。髭のモデルになった面もありますか?
須藤「僕たちがバンドをはじめたとき最初は4人組だったんですけど、僕はドアーズみたいなことをやりたくて、鍵盤やコーラスを入れたいなと思ってたんです。ちょうどその頃、mimic(佐藤康一)が自身のバンドを解散するってときで、〈髭に入りたいと思ってるんだよなー〉と言っていて。じゃあ、〈鍵盤できる?〉〈コーラスできる?〉って訊くと〈どっちもできるよ〉と。ちょうどいいなと思って入ってもらったら、鍵盤もコーラスもできなかった」
一同「(笑)」
須藤「で、そもそも彼はドラマーだったんで、それならドラムを2台にするとペイヴメントみたいでいいじゃん?ってなったんですよね。ペイヴメントは、そういう共通言語みたいなものとして当時からあった。
――ボブ・ナスタノビッチのことですよね。奇声を発しながらドラムやタンバリンを叩いたり、何を担当しているのか謎だけど妙に目立つ担当(笑)。
須藤「そうそう。ハッピー・マンデーズのベズとか、電気グルーヴのピエール瀧さんもそうですけど、当時は〈そういう存在がいてこそバンド〉みたいなムードがあった気がします」
――Homecomingsのお二人は、髭をきっかけにペイヴメントを知ったそうですね。
福富優樹(Homecomings)「そうなんです。僕は91年生まれでぜんぜんリアルタイムでもないし、彼らはロックの歴史本とかに大きく載るようなバンドでもなかったから、なかなかアクセスできなくて。でも、髭はデビューした頃から好きで、それこそ須藤さんたちがインタヴューやラジオで言及していたのを通じて、ペイヴメントと出会えました」
須藤「いや〜嬉しいです」
福富「僕らってそういう世代なんですよ。アジカンからウィ―ザーを聴きはじめたり、そういう紐付けがあったというか。髭の曲でいうと“GOO”“せってん”みたいな曲が大好きなんですけど、あとからペイヴメントを知ることで、自分はUSインディー感みたいなものが好きだったんだと気付かされました」
――畳野さんはどうでしょう?
畳野彩加(Homecomings)「(福富は)高校からの同級生なので、髭も教えてもらったし、その流れでペイヴメントも知りました。でも、最初に聴いたときは〈なんじゃこりゃ〉って感じで(笑)。ぜんぜんのみ込めなくて、髭のほうが良いなと思ってました。それが大学生になって、いろいろ聴くようになってくると……」
福富「5作目の『Terror Twilight』(99年)を聴いて、〈これこれこれ!〉みたいになったのを覚えています」
畳野「そうそう! あのアルバムを聴いて(魅力が)やっとわかった」

――橋本さんは、以前からHelsinki Lambda Clubのプロフィールで〈『ペイヴメントだとB面の曲が好き』と豪語する〉と書かれてましたけど。
橋本薫(Helsinki Lambda Club)「ハハハ(笑)。そうですね、僕は裏ペイヴメント的な曲が好きなんです。“Kennel District”とか“Date With IKEA”とか。なんならスティーヴン・マルクマスが歌ってない曲」
福富「スコット(・カンバーグ)が歌っているやつね」
橋本「ああいう曲のコード進行を一生やっていたいと思っちゃう。僕がペイヴメントに出会ったのはけっこう遅くて。中学・高校の頃は、オルタナでいうとニルヴァーナとかを聴いてたんですけど、大学のときに聴いたらすごくフィットして。そこからハマっていきました」

――どのあたりがフィットしたんでしょう?
橋本「ニルヴァーナとかだと、内省的な部分や怒りだったりをストレートに出している感じがしますけど、ペイヴメントは悲しみとかも、ちょっと茶化したり皮肉を加えたりして表現している雰囲気があるじゃないですか。そういうところが自分の気分に合ったというか」
須藤「僕もニルヴァーナを聴いたのは高校生ぐらいで、そのときは精神的にもシンクロして〈俺も長生きしないでいいよ〉ってなったりしたけど、少し年齢を重ねると〈そこまでシリアスに生きていけないな〉って思ったな。〈そこまで悲観的に世の中を見てないんだよね〉っていうか、うーん……そこまで悲しいかなって(笑)」
一同「(笑)」

須藤「少し大人になってくると、ペイヴメントくらいのほうがマッチしてくるんですよね。いや、カート・コバーンはもちろん素敵ですよ。僕はいまだに大好きだし、時間があればWikipediaとか見ちゃう(笑)。でも、あの人はあの人だと思っていて。自分はもっと世の中とマッチしているし、もちろんマッチしていないところも持っている。で、そういうマッチしていない部分って言葉では説明しづらかったりするじゃないですか。その〈説明できない〉ということを、ペイヴメントは音楽で表現していると思うんですよ」
――わかります。
須藤「説明できる人はカッコいいなと思いますけどね。亡くなった内田裕也さんのように、言い切れる人はロック・ミュージックとすごく相性が良いし。でも、そうじゃない生き方、アティテュードや表現を教えてくれたのが、僕にとっては90年代の中期くらいのミュージシャンだったし、そういう幅を示してくれたのがペイヴメントのようなバンドだった」
――そういうところが、若いリスナーやミュージシャンにも支持されている感じがします。
福富「好きな人が多いですよね。シャムキャッツやミツメもそうだし」
須藤「そこはやっぱり、マインドの部分が大きいんだと思うな」
――ルーズで斜に構えているんだけど、〈こういう人間がいてもいい〉と思わせてくれるところが。
一同「うんうん」
福富「ペイヴメントの場合は、そういう人間が5人集まっていたのも大きいですよね。前任のギャリー・ヤングを含めると6人か」
須藤「ドラマーいたよね。あいつも、なんじゃこりゃーみたいな奴で」
福富「彼のソロ作とかヤバいですよ。めちゃくちゃな内容で、ペイヴメントの人じゃなかったら1ミリも良くな……。ジャケットも衝撃的なので、ファンの人なら騙されたと思って、ぜひ聴いてみてほしいですね(笑)」
気持ちがこもっているからこそヘロヘロに歌うことでバランスがとれる
――みなさんがペイヴメントで好きな曲は?
須藤「うーん、どれだろう。アルバムだと2枚目の『Crooked Rain, Crooked Rain』(94年)と3枚目の『Wowee Zowee』が特に好きで、曲単位だと3枚目に入っている“Grounded” かな。あと、同じアルバムだと“Fight This Generaton”も。2部構成の曲で、最初は2曲分のつもりで聴いていました。でも、あとで確認したら〈これ変わってないの!?〉って。それまでポップソングというのは、〈ABCABCAB……〉と繰り返して3分くらいで終わるものだと思っていたけど、あの曲は〈A~~B~~〉みたいな感じで。それでも表現として成り立つんだって勉強になりましたね」
――ホムカミのお2人は?
福富「アルバムでは『Terror Twilight』がいちばん好きだから、収録曲の“Major Leagues”とか。あとは“Carrot Rope”も。やっぱりメロディーが良くて、メロウな曲が好きですね。だから、アルバムには入っていない“Give It A Day”(96年のシングル)も好きだし、僕らにとってのマルクマスはそういう存在なんですよね」
――ホムカミは昨年、『Terror Twilight』収録曲の“Spit On A Stranger”をカヴァーしていましたよね※。畳野さんは実際に歌ってみて、どんなふうに思いました?
※平賀さち枝とホームカミングス『カントリーロード/ヴィレッジ・ファーマシー』収録
畳野「めちゃめちゃ歌いづらい」
一同「(笑)」
畳野「メロディーだけじゃなくて、歌詞も独特な感じだけど。なんか良いなと思えたりもして。だから、どういう曲か理解しようというよりも、この曲が出た時代の雰囲気とかをイメージしながら、ホムカミなりにどう解釈できるかを考えてアレンジしました」
――ヘルシンキにも、ずばり“テラー・トワイライト”という曲がありますよね。
橋本「あれはもう、良いタイトルなのでそのまま拝借しました(笑)。いまの気分では4作目の『Brighten The Corners』がいちばん好きですけど、聴いた回数でいえば『Wowee Zowee』と『Terror Twilight』が多くて、それだけに思い入れもありますね」
――このように若い世代に人気のある『Terror Twilight』は、彼らにとってのラスト・アルバムにして、ある意味もっともペイヴメントらしくない作品でもあるのかなと。
福富「そうですよね。ナイジェル・ゴドリッチがプロデュースしていて、メンバーもそんなに気に入っている様子がない。これだけデラックス・エディションも出ていないし」
橋本「でも、最後のアルバムを“Carrot Rope”で締めてる感じもすごく良いんですよね。MVも含めて」
須藤「良いよねー、あのMVは泣ける。ペイヴメントってどのアルバムも、絶対に最後の曲が良いんだよね」
――次に、マルクマスが自分たちに与えた影響と言えば?
福富「僕らはギター・プレイかな。マルクマスはギター・ソロがめちゃくちゃ良いんですよ。すごく歌っているというか。音の外し方やチューニングの仕方も特徴があって、そのあたりはモロに……技術的にも影響を受けていますね」
橋本「僕は歌かな。マルクマスが下手だとは思っていないんですけど、ああいうヘロヘロな歌でもいいんだって部分にやっぱり勇気づけられたというか、自分でもやれるなと思った部分がある。気持ちがこもっているからこそ、逆にヘロヘロにすることでバランスがとれる感じとか。曲単位でいうと、僕らの“彷徨いSummer Ends”という曲は、完全に“Date With IKEA”とかの感じを意識しています」

――須藤さんは?
須藤「僕は子供のときから、技巧派を好きにならないところがあって。スピリッツを表現する人、生き方みたいなものを感じる人を好きになりやすいんです。そういう意味で、自分は力の抜き方を知っている洒落た人が好き。マルクマスもそうじゃないですか。ソロのファースト『Stephen Malkmus』(2001年)のジャケットとかびっくりましたもん。これ真面目にやってんのか、それとも狙ってんのかって」
――あまりにも爽やかですからね(笑)。マルクマスがソロになってから20年近く経ち、ペイヴメントよりもキャリアは長くなっているわけですけど、みなさんはソロも熱心に聴かれていますか?
福富「僕はソロもペイヴメントと同じくらい聴いています。ペイヴメントのことであれば全部を知りたいって感じで。ジックスになってからのアルバムもぜんぶ買っています」
須藤「ジックス良いよねー!」
――ソロ以降だと、どのアルバムが好きですか?
福富「やっぱりファーストかな。メロウで曲もしっかりしていて、好きな曲が多いんですよね」
畳野「私もソロのファーストをよく聴いたかな。Homecomingsの最初のアルバム『Somehow, Somewhere』(2014年)を制作したときにもよく聴いてたよね」
福富「うん。あのアルバム、アコギの音とか異常に良くて参考にしました。それ以外だと……ベックがプロデュースした『Mirror Traffic』(2011年)くらいからまたポップになってきて、ここ最近のアルバムは聴きやすいですよね。それまではわけわからん組曲みたいな曲とかもやってたけど、ペイヴメント再結成以降からまた変わった感じがします」
――須藤さんもさっき、ジックスがお好きだと言ってましたけど。
須藤「ソロ2作目の『Pig Lib』(2002年)が好きでした。あの蝙蝠が飛んでいるみたいなジャケットのやつ」
――あれもいいアルバムですよね。ペイヴメントのやろうとしていた先を狙ったというか。ちょっと実験的な曲や、ニューウェイヴっぽい曲も入っていたり。
須藤「そうそう、カッコよかったですよね」
福富「でも、今日の主役はこっちですから(新作『Groove Denied』を指さす)」