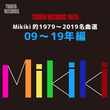瞬間的な決断で捉えた音
今作のスタイルについて彼はより饒舌に説明を続ける。
「前作との違いがどこにあるのかと言うと、新作は演劇を観に行くようなもので、前作はIMAXシアターで『トランスフォーマー』を観るようなもの。前作は何もかも限界まで押し広げられていて、強烈だったよね。で、IMAXシアターで映画を観ている時にトイレに行きたくなったら、その映画と感情的なコネクションを築けるってわけじゃないから、軽い気持ちで行ける。でもこじんまりした劇場で演劇を観ているとしたら、トイレに行きたい気持ちを我慢してでも、席を立たずに最後まで観たいと思う。だからこのアルバムは、ひとつの概念ではなくひとつの瞬間に立ち会っている気分にさせる、インティメイトな作品にしたかった。例えば何かが起きて、それを記録しているのだとしたら、新作で用いた手法は絵画ではなく写真に近い。写真は決定的な瞬間を捉えていて、人は、撮影に費やした時間より長い間、その写真を眺めるものだよね。それが新作であり、前作の場合は僕らが制作に費やした以上に長い時間、誰かがあのアルバムを聴き続けるってことはあり得ない。偉大な絵画作品ってそういうものなんだよ。画家が制作に要した時間を絵画の鑑賞にも費やすのだとしたら、いったい何時間眺めていたらいいのかわからないよね。でも写真なら事情は違う。瞬間的な決断で作られたものだから。つまり、このアルバムから僕が聴き取りたかったのは、文字通りに〈写真〉なんだ。それは、一度きりの出来事を捉えた音であって、二度と再現できない。だから僕らはファースト・テイクを使った。前作とは真逆なことをやったんだよ」。
もちろん新たな試みもある。当初BJトーマスやジミー・ホガースら外部のプロデューサー/ソングライターも交えて進めていた曲作りは、最終的に売れっ子のジャック・アントノフを共同プロデューサーに迎えて着地した。とはいえ「新鮮なエネルギーを持ち込んでくれた」というジャックの貢献もありつつジョージとマシューが主導する方向性には変わりなかった模様。〈わかってやっています〉感を説明してくれるあたりの雄弁さも実にモダンだが、利口にキャリアや見え方をコントロールしながら創作を続ける彼らにとって、シンプルでフレッシュな『Being Funny In A Foreign Language』もまた何かの布石かもしれないということだ。そんなふうに今後が読めないのも〈The 1975らしさ〉というわけで……。
「〈この札を切るのは早過ぎるのかな〉と感じた瞬間もあった。でもすぐに否定した。なぜって僕はここからさらに遠くまで行くことができるから。ただ、いま人々がThe 1975に求めているのはこういうアルバムだと思うんだ。僕は常に空気を読んでいて、この路線に飽きた時に――いまはまだ飽きていないけど――次に行くべき場所を見極めるんだろう。このアルバムは10年後に生まれたとしても成立すると思うから、あと2枚くらい未踏の域に踏み込むような作品に取り組んでからこういうアルバムを作ることもできたと思うけど、タイミング的には良かったんじゃないかな。年を取ってからこういうアルバムを作ったら、〈ああ、彼らはもう年寄りだから普通にロックをやりたいんだな〉って思われるかもしれないし(笑)」。
左から、ジョージ・ダニエルが参加したチャーリーXCXの2022年作『Crash』(Asylum UK)、ジャック・アントノフが在籍するブリーチャーズの2021年作『Take The Sadness Out Of Saturday Night』(RCA)、ベンジャミン・フランシス・レフトウィッチの2021年作『To Carry A Whale』(Dirty Hit)