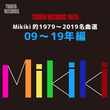溢れる情報をモダンな万能感で組み上げた大作群から一転、写真のように瞬間の音と感情をスナップしたニュー・アルバムは原点回帰を示す快作となった!
The 1975とは何か?
もはや説明の必要もないほど、同世代を代表する現行シーンきっての人気バンドとして一挙手一投足が注目されているThe 1975。現代的な内省をバックグラウンドにしたリリシズム、ユニークなサウンド・アプローチによるジャンルホッピングな感覚、SNSフレンドリーな話題作りなどが当代のリスナーにアピールしている彼らは、いまもっとも熱烈に語られるタイプのアーティストと言えるだろう。2002年にマンチェスターで結成され、2013年に『The 1975』でアルバム・デビューを果たしたThe 1975は、マシュー・ヒーリー(ヴォーカル/ギター)、アダム・ハン(ギター)、ロス・マクドナルド(ベース)、ジョージ・ダニエル(ドラムス)から成る4人組。前作『Notes On A Conditional Form』(2020年)に至るまでのアルバム4作すべてが全英チャートで首位に輝いている。日本でも早くから支持を集めていて、この夏には8度目の来日にして5回目の〈サマソニ〉出演をヘッドライナーとして飾ったのも記憶に新しいところだ。

そんな彼らが通算5作目にあたるニュー・アルバム『Being Funny In A Foreign Language』をいよいよリリースした。パンデミック期間の苦悩を経て制作された今作についてマシュー・ヒーリーはこのように説明している。
「当初はいろんなことを考えていて整理ができていなかったんだ。いったいどんなアルバムを目標にして作業をしているのかわからなくて、非常に曖昧な状態だった。制作プロセスがかなり進行するまで、僕らには明確なヴィジョンがなかったんだよね。だからとにかく、方向性を定めずに、たくさんの、いろいろ異なる断片を作っていた。そしてようやく方向性が定まった際に、それらの断片を聴き直して、どれが曲として成立しているのか選別を始めて、成立していないものは脇に避けておいたというか。で、曲として成立しているものに意識を集中させて、それらをスタジオで、機材を限定してレコーディングしたんだ。それでおしまいっていう感じだったよ」。
とりわけ3作目『A Brief Inquiry Into Online Relationships』(2018年)と前作『Notes On A Conditional Form』において創造の探究を野心的に極めた彼らだったが、今回は朽ちた自動車の上に立つジャケからも推察されるように(3作目の仮題は『Music For Cars』だった)、そうでなくても“Happiness”などの先行シングルで提示されていたように、ある種の揺り戻しがバンドに訪れているのは明らかだ。
「今回は全体的に、The 1975を原点に回帰させたいということだけはわかっていた。と言いつつ、僕らの場合はその原点に該当するものが、あまりにもたくさんある。例えばエレクトロニック・ミュージックとか、セカンド・アルバムの路線とか、サード・アルバムの路線とか。でも普通に考えれば、ブラック&ホワイト(=初作『The 1975』)こそが僕らの原点だから、最初の意思表示としてどの曲を選ぶべきかは明確だった。そして“Happiness”以降の意思表示もすべて〈ブラック&ホワイト〉になるよ」。
一聴しての感触はもちろん当人たちの意図した通りだったようで、多くの人がイメージする〈The 1975らしさ〉は、やはり初期からのバンドらしいバンドのサウンドだったということだろう。
「シニカルに聞こえたり人為的な印象を与えかねないネガティヴな言葉は一切使いたくないんだけど、このアルバムでは、これまででもっともコンセプチュアルなアプローチを採った。まあ、どのアルバムもいろんな意味でコンセプチュアルだけど、このアルバムは〈The 1975のサウンドとはどんなものなのか?〉と思い描いて作ったんだ。もしくは、〈何が人々をThe 1975に惹きつけるのか?〉とか〈The 1975を形作る基本的要素は何か?〉とか。これからも旅を続けていくにあたって、こういったことを一度見極めておこうじゃないか――という考えに則ったアルバムなんだよ。なぜって、僕らはあまりにも遠く離れたところまで来てしまったからね。〈The 1975とは何か?〉どころか〈バンドとは何か?〉という地点からも、随分遠い場所に来てしまった。だから、核心の部分での僕らがいったい何者なのかを自分たちに言い聞かせるのも悪くないんじゃないかと思った。そうすれば、そこからまた成長できるから。そこが素晴らしいんだ。この次に何をするのか、完全に白紙の状態になったわけだからね」。