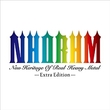コージー・パウエルのセミナーを受けて感激
――その頃は全然ジャズには興味なかったんでしょうか?
「いや、やっぱり興味はあったの。
70年代に野獣(NOKEMONO)でデビューしたギターの中野重夫さん――同郷の同じ高校の先輩で、演奏はジミヘンみたいなで格好良いんだけど――その人のバンドのライブを高校の時に観たのね。そのバンドのドラムの人がレギュラーグリップで、ミッチ・ミッチェルみたいに叩くわけ。ほとんど1コードだけで、ずーっとインプロをやっているのが衝撃的で、〈何だこれは〉と思って。
それで、ミッチ・ミッチェルからジンジャー・ベイカーを聴いて、〈じゃあ、そういうドラミングのルーツはなんなのか〉と、ジャズに興味を持って。そしたらコージーもルーツにルイ・ベルソンがいたから、〈じゃあ、ルーツの人を聴いてみよう〉と思って」
――コージー・パウエルにハマったのは、どこからなんですか? クリニックも受けてらっしゃいましたよね。
「最初に聴いたのは、やっぱりホワイトスネイクの『Slide It In』。小学生の時に聴いて、スカッとした叩きっぷりが凄く好きで。〈モンスターズ・オブ・ロック〉の映像も観て、〈ああ、こんなふうに叩いたら気持ちいいな〉と思って。
コージー・パウエルのクリニックは、90年で17歳の時。写真もあるよ(写真を取り出す)。

高2の時、ヤマハのドラムセミナー合宿で〈ドラマーズ・キャンプ〉っていうのがあって、スペシャル講師がコージーとピーター・アースキン(ジャズドラマー、ウェザーリポートなど)。もう一人いたけど忘れた。生のコージーを目の前で体験できて、感激だったよ」

――このセッティングはコージーのですか?
「そう、ちょうどこの頃のコージーのセッティングで、ブラックサバスの『Tyr』(90年)の頃。このアルバムはウォークマンでずーっと聴いてた。
こんな距離感で叩いてるんだなと思ったよ。この時、コージーはまだ41、42歳だと思う」
――初めて会ったドラムヒーローについて、特別印象に残ったことって覚えていますか?
「スイッチの入り方が凄かった。普段の姿や話している時と全然違って、いざプレイするとなると、演奏する時のパワーというか、そこに賭ける、なんというか……情熱というか、言い表しにくい凄みが出てきて」
――ピーター・アースキンの印象はどうでしたか?
「その時はコージー一辺倒だったし、ジャズは興味あったけど、ピーター・アースキンって全然知らなかったの。髭の、まるっこいおじさんって感じだったな。
でもね、当然だけど、叩くとすっごい良くてさ。スティックワークとか音色、ダイナミクスにびっくりして、〈えっ、これがジャズの人なの〉って。それでなおさらジャズに興味を持ったところがある。だから、ジャズの道に進んだのは、この時のおかげかもしれない」
アート・ブレイキーとエルヴィン・ジョーンズの謎めいた衝撃
――実際にジャズをプレイし始めたのはいつ頃ですか?
「その後、高校を卒業して東京に出て武蔵野音楽学院っていう専門学校に行って、その時の同期の人たちと空き時間に練習とかセッションをして、だんだん広げて(東京・新宿)ピットインの昼のジャムセッションに行くようになったの。そこで色んな人の演奏を聴いて知り合って、少しずつ呼んでもらうようになって。奏法や音楽的に足らない要素を徐々に発見して、色んな目標が出てきた」
――東京にはジャズをしようと思って出てきたんですか? バンドでもなく。
「プロでやっていきたいなっていう思いは最初からあったんだけど、その頃はまだ〈いつかはジャズもやってみたいな〉っていう感じで。色んなミュージシャンと知り合いになって演奏できたらなとは思っていたけど、最初から〈ジャズドラマーでやりたい!〉って感じではなかったと思う。
ただ、武蔵野音楽学院はジャズ系だったから、ジャズミュージシャンになりたい人が周りに多くて、そっちの方に目が行くっていうか。その頃にはエルヴィン(・ジョーンズ)とかを聴いてジャズばっかりやってたから、当時のコージーの作品は聴いてなかった」
――最初にジャズドラムで凄いと感じたドラマーって、誰でしたか?
「本当に最初に自分で買って聴いたっていうのは、アート・ブレイキーのCDだった。1950年代のブルーノートのライブ盤だね。
もう何をやってるのかわからないわけ。今まで、かっちりした楽曲しか聴いたことがないのに、アドリブで平気で10分とかやってるし、〈これは一体なんなんだ〉と。かたや、こっちはバスドラとスネアで〈ドンパンドンパン〉の世界やってたわけだから。
ロックってさ、いわゆる大サビとかで盛り上がった時にシンバルにいくけど、ジャズってずっとシンバルが鳴りっぱなしでしょ。それに凄く 興味があって、その辺かな。それを解明したいなって思った。
あとは、さっきも言ったエルヴィン・ジョーンズとか。最初によく聴いていたのは、ソニー・ロリンズの『A Night At The Village Vanguard』(1958年)とか、ジョン・コルトレーンの『My Favorite Things』(61年)とかで、だんだんエルヴィン自身の『Heavy Sounds』(68年)とかのリーダー盤を聴くようになったんだけど、あれも謎に思っていた。
何が起こっているのか全然わからない。ブレイキー以上によくわからなかった。ブレイキーは、ロングソロもあるし、音符もわりときちっとしてるじゃない。マックス・ローチも。だけど、エルヴィンって、合っているのか合っていないのか、ハマっているのかハマっていないのか、よくわからない。結構荒っぽく聞こえるし、そうところに興味を惹かれた。実際はそうじゃないないんだろうけど、〈バタバタ、ドシャーン〉って聞こえるし、それが楽しいっていうか、刺激を受けたんだよね」