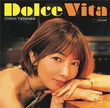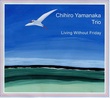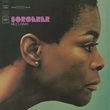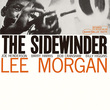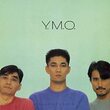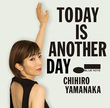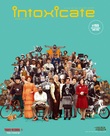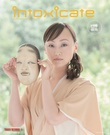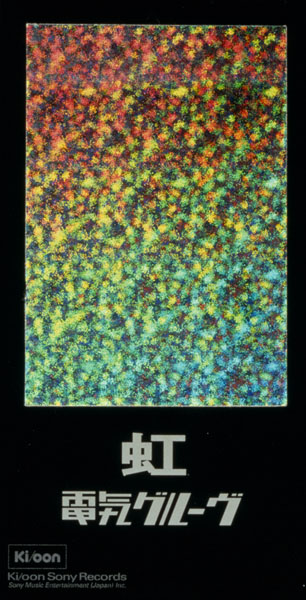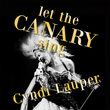自然の造形美のようなウェイン・ショーターの表現
――話を戻しますが、ウェイン・ショーターのどういうところに一番惹かれるのでしょう。
「まったく予期できないところですね。ソロが始まると大体の人はこんな感じかなというのがあるじゃないですか。でも、ウェインは何回聴いても自分の予測とは違うところに行く。想像の斜め上どころか、〈ええ!?〉っていうところに彼は行くんですよ」
――音楽観がかけ離れていますもんね。ぼくは、彼を〈電波〉の人と称えたりします。なんか得体の知れないものと交信しているような……。
「(笑)。アンテナが立っている。そういう感じの人ですよね。この世のものではない音楽が来ますよね。
あと、まったくどの形にも合わない。たとえば、彼はかつてビバップとかハードパップの時代にいましたけど、ハードバップとはまったくスタイルが違う。でも、だからこそどんな時代になっても朽ちることがないんです。そういう面でもおもしろいですよね。
私自身、ウェイン・ショーターの表現から感じるのは、自然の造形美のようなもの。たとえば、雪の結晶のような。私たちの計算では計り知れない美しさがあり、その美しさがすごく好きです」
――アルバムの1、2曲目“Dolce Vita”“To S.”は山中さんのオリジナルですよね。3曲目“Stranger”は誰の曲でしょう?
「久保田早紀さんの“異邦人”です」
――ウェイン・ショーターで、なぜ“異邦人”?
「ウェイン・ショーターの曲を録った後に、そこからインスピレーションを得た曲が生まれてきてしまって、これはやりたいと思い、追って録音しました。でも、その後にウェイン・ショーターの曲が来るのはどうかなと思ったんです。申し訳ないんじゃないかと……」
――変なところ、殊勝なんですね。
「(笑)。そこでウェイン・ショーターの曲に入っていくためのトランジションが欲しくて、久保田早紀さんが大好きだったのと、メロディがウェイン・ショーターの哀愁を帯びたテイストと重なるちょっと中東風の雰囲気があるので、“異邦人”を選びました。ウェイン・ショーターの音楽にもそういう民族音楽的なものが入ったりもするじゃないですか。
今作は坂本龍一さんにも捧げているんですけど、それらの導入としてガラリと雰囲気を変えるために入れました」
ウェイン・ショーターや坂本龍一の音楽が私の燃料
――アルバム冒頭に置いたオリジナル曲には、ウェイン・ショーターに対する思慕の一番どんな部分を出せればと考えたのでしょう。
「ウェイン・ショーターの曲にはそれこそ“Speak No Evil”や“Fee-Fi-Fo-Fum”のようなモーダル、でもちょっとブルージーな曲があったりするんです。たとえば、2曲目の“To S.”はそこから着想を得まして、実はコード進行を部分的に使っています。
彼の曲って予期しないような、普通はないような転調があったりしますが、そこにちょっとオマージュしました。それは、坂本さんもそうなんですけどね。
1曲目の“Dolce Vita”はお亡くなりになったウェインや坂本さんに少しでも自分がそこに近づきたいという思いを、前へ前へと行くようなコード進行に託しました。彼らを追いかけたい。そういう気持ちの表れたコード進行にし、それにメロディーを乗せてみました。
最初の部分はちょっと激しいですが、それは彼らの音楽が私の燃料ですので、いただいたエネルギーで自分もロケットを発射するみたいにいろんな音楽を生み出したいという気持ちが出ています」
――アルバムタイトルの『Dolce Vita』は、そのオリジナルの曲名でもありますよね。
「『Dolce Vita』はイタリア語ですが、英語だと〈ビューティフル・ライフ〉という意味もあるんです。ウェイン・ショーターと坂本龍一さんお2人の音楽に出会えて、みなさんの人生がいかに美しい人生になったか。そして、彼らの人生もすごく美しい。そうした尊敬の念も込めて、このアルバムタイトルにしました。
イタリア語にしたのは、ウェイン・ショーターと初めて会って話したのが、イタリアのウンブリア・ジャズ・フェスティバルに出演したときだったからです」