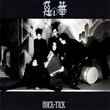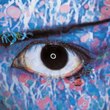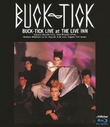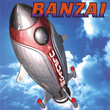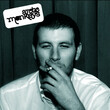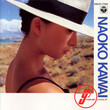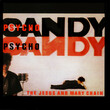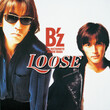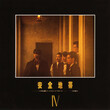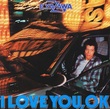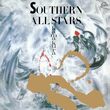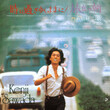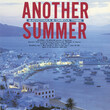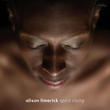BUCK-TICKの8作目のアルバム『Six/Nine』がリリースされたのは1995年5月15日で、もうすぐ30周年を迎える。日本やイギリスなど各地のスタジオで膨大な時間をかけ録音されたこと、故ISSAY(DER ZIBET)が参加したこと……とトピックは多いが、特にダークな歌詞世界と電子音楽やインダストリアルミュージックの要素を取り入れたサウンドのアプローチは彼らのディスコグラフィの中で独自の輝きを放っている。そんな名盤の深奥に李氏(音楽ZINE「痙攣」編集長)が踏み込んだ。 *Mikiki編集部
グランジ以降の折衷的音楽性と内省的な歌詞
「大げさに言うと、自分では神がかったかのような、何かが乗り移っちゃったかのような作品」――当時のツアーの打ち上げでボーカル櫻井敦司が自らこう語ったように(「WORDS BY BUCK-TICK 1987-2002」シンコーミュージック、2002年)、『Six/Nine』(1995年)という作品には、バンドの音楽的野心とリリックにおける深化、彼らを取り巻く時代性といった要素が(それこそ神がかり的に)合致したような凄みがある。
グランジ以降隆盛したオルタナティブメタルとミニストリー影響下のインダストリアルロックという二つの音楽的潮流の合流。そこにトリップホップやアンビエント、シューゲイザーやダブといった様々な手法を取り込んだことで、『Six/Nine』独自の折衷的な音楽性が成立したとひとまずは言えるだろう。さらにリリックにおいては輪廻をモチーフに内面のネガティビティを深く掘り下げた作風を追求し、ニルヴァーナ以降のロックミュージックの内省化の流れと共振を示した。
90年代BUCK-TICKの音楽的探究の集大成
このように一応はまとめることのできる今作だが、しかし同時に90年代以降のBUCK-TICKの音楽的探究の一つの集大成としての側面を持っていることを忘れてはならない。
『狂った太陽』(1991年)、この彼らの最大の音楽的転機と言える傑作においてそれは始まった。前作以前のビートロックの引力をリズムの面でもサウンドの面でも振り切り、厚みのあるダークなサイケデリアをインダストリアル以降の電子音響で彩った同作はまさしくバンド史上最大の画期の一つとなったし、加えて終盤3曲に象徴されるデスパレートな内面表現は確かに『Six/Nine』と繋がるものがある。
リズムの刷新。ダークなサイケデリアの表現。内面のネガティビティの掘り下げ。これらは次作『darker than darkness -style 93-』(1993年)においてゴスとインダストリアルダブを融合させ結果的にポーティスヘッド『Dummy』(1994年)に1年先駆けた“キラメキの中で・・・”を筆頭に、より深くより広く追求されることとなった。さらに同作が重要なのはグランジ以降のヘヴィネスを本格的に導入したことにあるだろう。例えば“青の世界”で聴くことのできる重厚なギターサウンドは彼らの優れた同時代性を物語っている。これら非ロック的なリズムの導入、ダークなサイケデリアの追求、同時代的なヘヴィネスへの傾倒、リリックでの内省性といった要素は2年の時を経て『Six/Nine』へ結実していく。