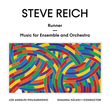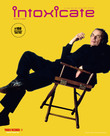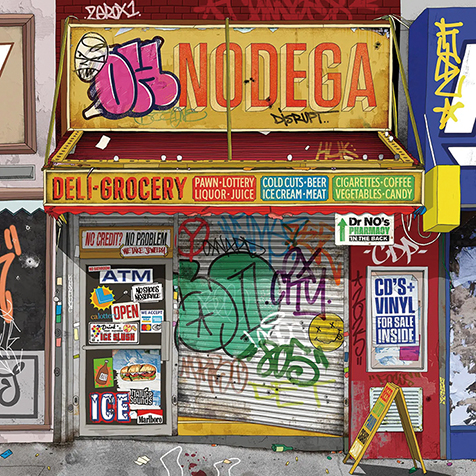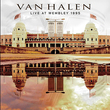ジョニー・グリーンウッドとの出会いから生まれた『レディオ・リライト』
スティーヴ・ライヒの新譜は、ある意味、異色のつくりになっている。それは、現役の、しかも若いミュージシャンによる音楽との相互性がかたちになっているからだ。いま、この文章を読まれている方にとってはもう了解済みのこととおもうが、ライヒはUKのロック・バンド、レディオヘッドの作品にもとづいた作品“レディオ・リライト”があり、その一方でレディオヘッドのメンバー、ジョニー・グリーンウッドによる“エレクトリック・カウンターポイント”がある。そのあいだに“6台のピアノ”を新たにピアノと多重録音テープにした“ピアノ・カウンターポイント”を収録。
ちょうどライヒ自身への電話インタヴューが可能となったので、いくつかの質問を用意して、以下の返答を得ることができた。
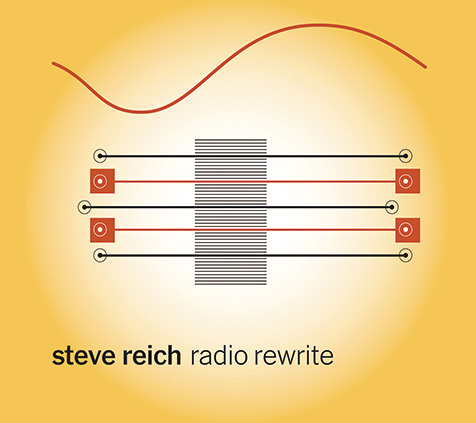
――新しい作品が生まれた経緯、そして、アルバムの構成について教えて下さい。
「新しいアルバム、タイトルは『Radio Rewrite』というんだ。はじめ、ロンドン・シンフォニエッタに新しい作品の依頼を受けて、作曲を始めた。でもなかなか順調には進まなくて、そのとき作っていたものを却下したんだよ。同時期、つまり2010年頃なんだけれど、ポーランドで開かれる音楽フェスティヴァルに招かれた。そこはニュー・ミュージック、新しい音楽を紹介するフェスティヴァルで、コンテンポラリー・コンサート・ミュージックとロック・ミュージック界から、それぞれミュージシャンが参加していた。そのなかの1人がジョニー・グリーンウッドだったんだ。
私が昔パット・メセニーの為に作曲した“エレクトリック・カウンターポイント”を演奏するためにジョニーは参加していた。それをきっかけにジョニーついて少し調べ始めたんだな。ジョニーは元々ヴィオラを弾いていた。オックスフォード大学で教育を受けて、後に作曲家として、映画『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』(監督:ポール・トーマス・アンダーソン)のスコアなどを書いている。その後、映画を見て気づいたのだけれど、おもしろいことに、そのスコアはオリヴィエ・メシアンのひびきに似ているんだ。知らずに聴いていたら、まさか作曲した人物がロックスターだとは思いもしなかっただろうね。
ポーランドで聴くことのできたジョニーの“エレクトリック・カウンターポイント”の演奏=解釈は本当に美しかった。その後直接会って、会話を交わすことも出来て、いい時間が過ごせたんだ。もちろん数年、いや、もっと前からレディオヘッドの名前は耳にしていた。だけど、1音符も聴いたことがなくて、恥ずかしかったんだよ。ジョニーにせっかく会ったというのにね。で、帰ってすぐインターネットで調べ、曲を聴いたりヴィデオを見たりしたわけだ。 10曲ほども聴いたかな。そのなかの2曲が気になった。『キッドA』(2000)に収録されている“Everything In Its Right Place”と『イン・レインボウズ』(2007)の“Jigsaw Falling Into Place”だ。この2曲が凄く気に入ったということももちろんある。前者については、特にサビの〈Everything〉というフレーズを運ぶメロディに感銘を受けた。この短いフレーズに西洋の和声の基本となるものが聴き取れるんだな。もう1つの曲もとても美しくて、この2曲を元に、もちろん内容は変え、私の色に染めたうえで新しい楽曲を作ったというわけだ。もちろんこれは私の、スティーヴ・ライヒの楽曲なんだよ。レディオヘッドが聴こえるかって? うん、その答えは、どうかな。若干聴こえるかもしれないけれど、基本的には聴こえないだろうな。エレキベース以外は、ロック楽器ではなく、コンサート楽器のために書かれているしね」
――ジョニー・グリーンウッドの演奏=解釈について、作曲者として感じる、考えることは?
「さっき少し触れたけど、ライヴでは本当に素晴らしいパフォーマンスを披露してくれた。だけどね、アルバムに収録されている曲とは較べものにならないな。この楽曲で聴こえるエレキ・ギターの音のほとんどは事前に録音したもので、ジョニーはバッキング・テープでは、それぞれのパートを様々なギターで、再録音している。ポーランドで聴いたものを遥かに上回る豊かな音質が得られているんだ。そんなわけで、このアルバムのヴァージョンはかなり良いものになっているよ」