テーマはさまざまな変容をとげた日本の歌謡曲&ポップスについて
坂本龍一監修による音楽の学校〈schola〉。第16巻のテーマは〈Japanese Pop Music〉。すなわち日本の歌謡曲&ポップスについての講義である。鼎談では、人形浄瑠璃や官軍の行進曲など起源について考察を巡らせつつ、ラジオやレコードというメディアが普及する昭和以降の楽曲を採り上げ、雑多なジャンルのごった煮である歌謡曲、そこから派生したわが国ならではのポップスが世につれながらどのように変化・発展していったのかを追っていく。目に見えにくい歌謡曲の実体の境界を探る作業である。
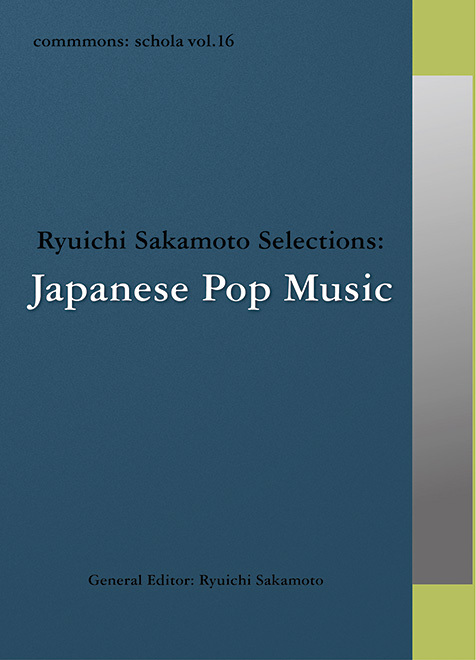
当然ながら話題は多岐に渡り、処理しきれない箇所も所々に登場するのだが、読み進めていくうちに曖昧さこそがそもそも歌謡曲の魅力なのであるということが理解できる仕組みになっていて、なるほどと思う。話に熱が入るのは、何が歌謡曲で何がロックか、という永遠のテーマについて。その境界線付近に身を置き、その差異を身体で感じていたはずの教授が日本語ロックのパイオニアとして挙げているのは誰か(彼らこそロックと歌謡曲の境界の垣根を曖昧にしたミュージシャンだろう)。また、歌謡曲性とは何か? という問いを受けて、彼が思わず発してしまうひと言にも注目されたい。そんなテーマを反映してか、同梱されたCDに登場する面々も実に雑多だ。榎本健一や二村定一といった浅草オペラの出身者から、昭和歌謡の筆頭格である坂本九、藤圭子を経て、加川良、荒井由実、くるりといったフォーク/ロック畑の楽曲がセレクトされており、何故かASA-CHANG&巡礼に着地するところがschola的で実にユニーク。それにしても、ページを捲りながらつい考えてしまうのは、2013年12月30日にこの世を去ったあのお方、第8巻にフィーチャーされた日本の歌謡曲&ポップス界屈指の理論家であるあの人のこと。もし彼が生きていて本書に参加していたらどんな切込み方をしていたのか。CDに登場する彼プロデュースによるシュガー・ベイブ《DOWN TOWN》を聴きながら想像を巡らせていた。



























