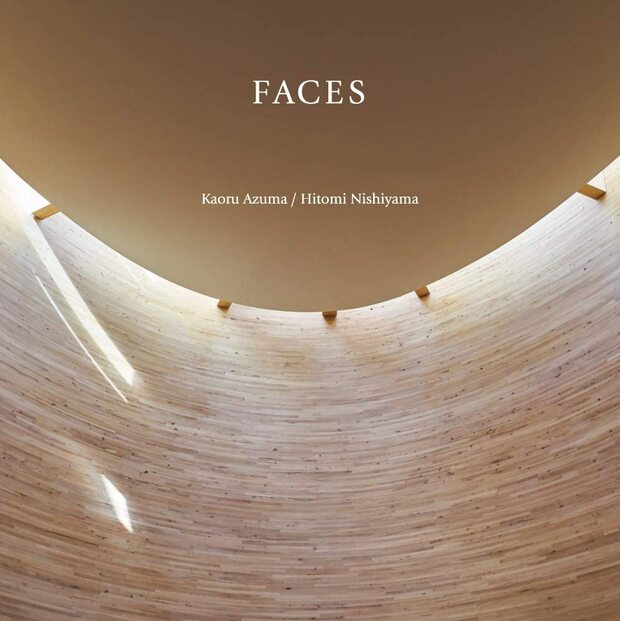ピアニストの西山瞳と、関西で活動するヴォーカリスト東かおるのコラボレーション作『Faces』が9月23日にリリースされる。二人の共演作は2013年の『Travels』以来7年ぶり。参加メンバーは『Travels』と同じ市野元彦(ギター)、橋爪亮督(サックス)、西嶋徹(ベース)という息の合った面々だ。西山瞳に、『Faces』をめぐるあれこれ、そしてコロナ禍の時期における〈一人のジャズ・ミュージシャンの生活と意見〉を語ってもらった。
インストの曲に歌詞をつけて歌う
――東かおるさんと久しぶりのコラボ作ですが、先に曲があってそれに東さんが歌詞を付ける、という方法で曲作りをしたんですね。
「7年前の『Travels』のときと同じで、私の曲に歌詞を付けてもらいました。もともとインストでやっている曲が多いので、こっちは咀嚼が進んでいて、そこに後で歌詞を乗せて歌ってもらうのはけっこう大変だろうな、と思いますね」
――西山さんの曲作りは時間をかけてやっているんですか?
「曲はいっぺんには出来なくて、1曲ずつ丁寧に積み上げていく感じでしたね。東さんは単に歌詞を付けて歌うだけでなく、歌として披露できる状態にするまでにかなり時間がかかると思います。今回は私がライブでやっていた曲が多いので、しかも共演者とも何度も一緒にやっていてウォーミング・アップができている感じだったので、歌の負担はけっこう大きかったと思います」
――メンバーも前作と同じですね。
「ドラムレスというのは最初から決めていて、最初は上モノにもう一人管楽器を入れようかな、とも思ったんですけど、最終的にやめました。メンバー全員が人柄も演奏も穏やかな人たちで、居心地がいいんです。そこにひとりだけ後から入ってがんばってもらっても、その人にもメンバーにも負担がかかるのかな?と思って」
――この5人ではライブも何度かやってますよね。
「このメンバーでのライブは年1回ぐらいです。東さんが関西だということもあるし、メンバー全員の予定がなかなか合わないんですよ。東さんと私のデュオは関西で年2〜3回やっていて、そのときに新しい曲をやっていました」
――今回の録音のための新曲はあったんですか?
「今回歌用に新しく書いた曲はないですね。もともと何かのアルバムに収録されていたインスト曲に加え、普段から曲をたくさん書いていてCDに採用されなかった曲も多いので、その中から歌に向いている曲をアレンジし直して採用した、というものが多いです」
――2曲、歌詞のない曲も入っていますが、それは?
「あの2曲は始めからヴォーカリーズでやってもらおうと。あれはもうインストですね」
――全体的にヴォーカルと伴奏という感じではなく、バンドっぽいサウンドですよね。
「それはうれしいです。メンバーもヴォーカルのバックという意識はないんじゃないですかね。ミックスも実はそれを意識してやっています。ヴォーカルのアルバムだったら、本来は歌が前面に出るミックスが普通なんでしょうけど、そういう意図で作っていないので、バンド全体のサウンドを混ぜ合わせようと思って、時間をかけてミックスしています。ミキシング・エンジニアさんの音楽の理解がすごく重要なんだな、と今回は特に思いました」
――音を聴くと、西山さんはリーダーとしてサウンド全体を見ている、という感じですね。あと、今回特に思ったのは、西嶋さんのベースの音の素晴らしさです。

「『Travels』のときは、ちょっとECM(レコード)的というのかな、少し靄がかかったような雰囲気にしたんですけど、今回はやり方をかえて、録音エンジニアはストレートなジャズ的に録る方にお願いして、ミックスは別の方にやっていただきました。それが上手くいったみたいで、音に関してはとても満足しています」
――前回も思ったんですけど、市野元彦さんのギターと東さんの声って異様に相性がいいですよね。
「本当に。『Travels』を作ったときに、彼女の声質に合う楽器は何かな、と考えて、最初はトロンボーンがいいなと思ったんですけど、彼女がNYで録音したアルバムにトロンボーンが入っていたので、じゃあ市野さんにお願いしようと。それでやってみたら、二人だけで豊かなハーモニーが感じられるんですよね。ライブしてても、なんかお風呂に入っているみたいな、いいお湯でした、という感じです」

――橋爪亮督さんのサックスも、非常に優しくて東さんの世界に合ってますね。
「みんな自分のプレイだけじゃなくて、全体のサウンドを考えてくれる人たちですね。みんな、ライブ会場の入口のドアのあたりで聞こえる音をイメージして演奏する、というタイプなのかな。どこでもいつも同じ音量でがーっと演奏する人もいるし、それも良いですけど、私も含めてみんな、演奏している場のことを考えるミュージシャンなんだと思います。でも最近、そういう人が以前より増えてきているんじゃないですか?」
――以前は根性派が8割、空間派が2割くらいのイメージだったけど、だんだん逆転しつつある?
「そうそう、どっちもできる人もだんだん増えてますしね」

メタルの曲を演奏して得たものは
――ところで、西山さんはここ数年メタルの楽曲をピアノ・トリオで演奏するという試みをなさってますね。メタルを研究することで、曲の作り方や音楽へのアプローチが変化したということはありましたか?
「そうですね、音楽の受け手のことをもっと考えるようになりました。メタルを採り上げる場合は、メタルのファンとジャズ・ファン両方に届ける、ということをすごく意識してやっているんですね。ジャズだとどうしても自分の音楽を追求する、ということが先にあって、音楽をどこに届けるか、ということには注意が少なかったのかも、と反省しましたね。
今回のアルバムでも、ここではベースを聴いてもらいたい、とか、聴き手に向けてアレンジするようになっていて、前回より交通整理がされている、と思います。前はミルフィーユ状に要素を乗せて乗せて、という感じだったんですけど、今回は要素を減らしてますね。曲のメロディーの作り方は変わっていないと思いますけど、アレンジが変わったのかな」
――私は“Manouche(マヌーシュ)”という曲がすごく印象的でした。まるでミシェル・ルグランみたいな、フランスっぽい美しいメロディーですね。
「あれはけっこう古い曲で、ピアノとクラリネットのデュオのために書いたものです。最初マヌーシュの音楽みたいな曲を、と思って書き始めたんですけど、コードの展開がえらいことになってきたのでそうならず、曲名だけが“Manouche”になりました」
――フランスといえば、“Pierre Without A Face”の歌詞は一部フランス語ですね。
「あれは、もともとのインストの曲があのタイトルなんです。家にある顔のない人形にピエールっていう名前を付けていて、たまたま目に入ったから付けただけなんですけど、東さんが〈ピエールいうたらフランス人やん〉と言って、ストーリーをひねり出してくれたんです」
――なんと(笑)! もっと深いストーリーがあるのかと思っていました。

「関西のシンガーって、ステージでしっかり喋れないとダメなんですよ。この曲を始める前に彼女が浪花節的なストーリーを語る、という芸が成立してしまってて」
――それは聴いてみたい! そうか、関西のシンガーは歌だけではダメなんですか?
「おもしろい話をみんなするんですよ。かおるちゃんも昔歌のお師匠さんに、〈関西でジャズ・シンガーやっていくなら、歌半分、喋り半分や!〉と言われたって。でも実際そういう感じなんですよ。お客さんがそれに慣れちゃっているから、よそから来た歌手の人は緊張するでしょうね」
――最後の“Night”だけ、西山さんが日本語で作詞されていますね。
「前のアルバムでも1曲作詞したので、今回もないとさびしいな、と思って、がんばって作りました。作詞は難しいですね」
――ということは、作詞作曲・西山瞳という楽曲は……。
「これで2曲です。歌詞を作るのはめちゃめちゃ時間がかかりました。内容だけでなく、音韻のことも考える必要がありますので。自分で作詞作曲した歌を、歌手の人が歌うのを聴くのはおもしろいですね。自分の手を離れる、という感じがして」
――1曲だけスタンダードが入っていて、『Travels』のときは“Moon River”、今回は“Fly Me To The Moon”です。どっちも誰でも知っている曲ですね。
「他の曲は誰も知らないので、あえてここはベタベタに、みんなが知っている曲をやろうと相談してます」
――東さんとのデュオ・ライブではスタンダードもやってるんですか?
「はい。ライブは凹凸が必要なので、お客さんが知っているスタンダードもやっています。ベニー・ゴルソンの曲なんかもやりますね」
――スタンダードを集めたアルバムも聴いてみたいですね!
「あはは、そうですね。オリジナルをやると、彼女も私もいいものを作ろう、という欲望が前面に出ますけど、スタンダードだとそれが外れるので、純粋に楽しんで演奏してます。聴いている人の休憩にもなりますね」