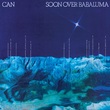Trafficによる大規模なリイシュー・プロジェクト
そんなカンのカタログが2000年代半ばにリマスターされ、CDとしてリイシューされた際、多くのリスナーやミュージシャンたちをインスパイアしたものだった(もちろん、当時高校生だった私もその一人だった)。それから10余年、ひさしぶりにカンの大規模なリイシュー・プロジェクトが日本盤のリリース元であるTrafficによって2020年7月から順次行われている。そして、11月にはついに全スタジオ・アルバムが出そろった(『Anthology』のみ2021年1月15日にリリースされる)。
今回はなんと、失敗作として葬り去られていた不遇のアルバム『Out Of Reach』(78年)も正式にディスコグラフィーに迎え入れられ、CD化された。また、2012年に発表されてファンを驚愕させた秘蔵音源集『The Lost Tapes』や、94年の2枚組ベスト・アルバム『Anthology』もシリーズに含まれており、なんとも掴みがたいカンというバンドの全体像を知るにはもってこいのラインナップになっている。


とりわけ、3枚組の『The Lost Tapes』は重要な作品だ。というのも、カンはレコーダーを回しっぱなしにして録音したのちに編集する制作手法を取っていた。なので、未編集の録音や貴重なライブをこれでもかと収録した同作には、彼らのエッセンスが生のままで詰まっている。

カンのリズム&グルーヴを再発見
カンといえば、マルコム・ムーニーが在籍していた『Monster Movie』(69年)や、ダモ鈴木がヴォーカリストだった『Tago Mago』(71年)、『Ege Bamyasi』(72年)、『Future Days』あたりが代表作として有名だろう。しかし、私が今回カンのカタログを聴き直して再発見したのは、ダモ鈴木が脱退したあとの『Soon Over Babaluma』(74年)や『Flow Motion』(76年)だった。緊張感と開放感がないまぜになったセッションを聴かせる前者も、レゲエ/ダブからの影響が強く表れたとびきり楽天的な後者も、とてもカンらしいレコードで、彼らの世界にどっぷり浸ることができる。


また、ジャマイカ人ベーシストのロスコー・ジーとガーナ人パーカッショニストのリーバップ・クワク・バーを突如新たなメンバーとして加えたことで評価が分かれている『Saw Delight』(77年)も、とてもいいアルバムだと思った。15分にわたってコズミックなグルーヴがうねる“Animal Waves”はいま聴いてもとにかく圧倒的で、その陶酔的な反復に身を委ねずにはいられない。

これらのアルバムは一般的に後期の作品とされ、かえりみられる機会は少ない。過小評価されている、と言ってもいい。しかし、カンの作品であるということすら忘れ、虚心坦懐に耳を傾けてみると、なんと心地よいリズム&グルーヴかと驚かされた。いずれも、いま〈家聴き〉するのにぴったりだと思う。
「カン大全」に見るバンドの本質
さて。一連のリイシューにあわせてele-king booksから刊行されたのが、松山晋也の監修による「別冊ele-king カン大全――永遠の未来派」である。
同書には、シュミット、シューカイ、リーベツァイト、カローリという中核メンバー4人とダモ鈴木へのインタビューがアーカイヴされており(シュミットとシューカイは3本ずつ)、さらに多彩なコラムと、ソロ作品を含めた包括的なディスコグラフィーの解説などが収録されている。2018年に英国で伝記「All Gates Open: The Story Of Can」が上梓された(また、89年に「The Can Book」という本が刊行されているらしい)ものの、まるまる一冊、これほどまでにカンを深く掘り下げた日本語の書籍なんて、史上初めてじゃないだろうか。バンドのバイオグラフィーはもちろん、戦後ドイツという時代、現代音楽やフリー・ジャズといった音楽的な背景、そしてメンバーたちの思考など、カンを知るための一級の資料が集められており、カンから無限に広がっていく音楽宇宙の一端に触れることができる稀有な一冊である。
「カン大全」に収められたメンバーへのインタビューを読みすすめると、謎多きカンの音楽の秘密がすこしずつ解き明かされていく。
たとえば、シュミットはこう語っている。「ヤキはいつも、ものすごく注意深くドラムをチューニングしていた」。たしかにリーベツァイトのドラムの音色は独特だ。和声とグルーヴとは緊密な関係にあるのだ、と述べるシュミットの語りからは、カンというバンドの本質をあらわにしているように感じる。そう気づいてからカンのカタログを聴きかえすと、また発見がある。
同書で何度も言及されているように、カンのもっとも重要なコンセプトのひとつに〈スポンテニアティー(自発性、自然発生性)〉というものがある。スポンテイニアスな演奏とは直感に従っている反射的なものだと思いそうになるが、しかし「カン大全」を読めばわかるように、それは経験や知識、ミュージシャンシップに裏打ちされているからこそ湧き出ているものなのだ(もっとも、非ミュージシャンだったムーニーやダモ鈴木は、真にスポンテイニアスな感覚の持ち主だったのだろうが)。そういったことも新しい発見だった。