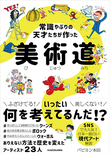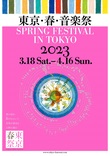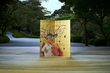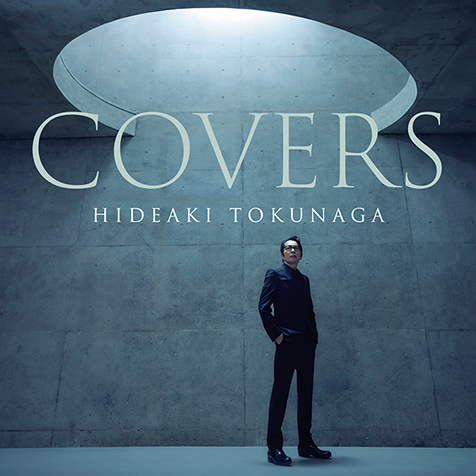私たちが意識せざるをえなくなった〈日常〉
日常と非日常のあわいにある〈現在〉とは?
あたりまえだった日常がどこかに行ってしまい、そのかわりに見慣れない日常があたりまえのような顔をしてやってきた。どうにもできないそのズレを現代美術作家はどう受け止め、表現するのだろう? 金沢21世紀美術館で開かれている〈日常のあわい〉展では7組の作家たちがそれぞれに〈日常〉を語る。
7組の中でもっともストレートに〈新しい日常〉を表現しているのが小森はるか+瀬尾夏美だろう。「みえる世界がちいさくなった」は2019年から〈震災後、オリンピック前〉というテーマで始めたプロジェクトが元になったもの。そこに2020年からの〈コロナ禍〉が重なって、プロジェクトの様相も変化した。会場では自粛生活を送る東京の若者3人の声をとらえた映像や、瀬尾が書き続けてきた〈コロなか天使日記〉などが並ぶ。

青木陵子+伊藤存の展示室に並んでいるのは宮城県沖にある網地島の空き家に残されていたものや、〈使えなくなったコード類〉といったモノを組み合わせたインスタレーションだ。そこには〈私達みんな似たとこあるよね〉〈大きな部屋の中にいると思っていたが、小さな部屋の中にいたのかもしれない〉といったサブ・テキストのような文章がつけられている。ありふれたモノの集積が何かを語りかける。

ささやかな日常で見逃しているものに注目したのが下道基行だ。彼の〈ははのふた〉は、下道の義母がポットの蓋として代用しているものを撮ったもの。カップ、小皿、保存容器の蓋といったものがアクロバティックにポットの口を覆っている。義母にとってはこれが日常だけれど、他の人から見るとちょっと奇妙に映るかもしれない。が、日常の細部はそんなものでできている。

元ダムタイプの小山田徹は、家庭ではお弁当の当番だ。あるとき、幼稚園の息子さんの弁当を作ろうとしたら、お姉さん(娘さん)の香月さんが〈こんなお弁当作ったら喜ぶんじゃない?〉と提案してくれたのが〈お父さんの顔〉をかたどったお弁当だった。香月さんのお題は〈みちの下(の地層)〉や星座の〈夏の大三角形〉など次第に難易度を増す。小山田さんはこれを「アートとして出すつもりはなかったけれど、生活の中の何かのヒントになれば」という。「毎日が大喜利」と苦笑しながらも楽しそうだ。