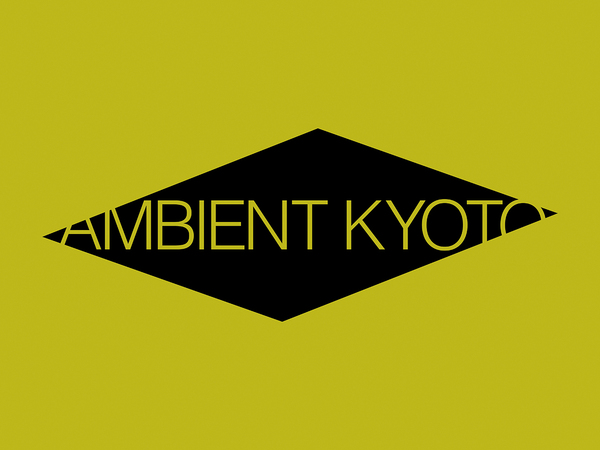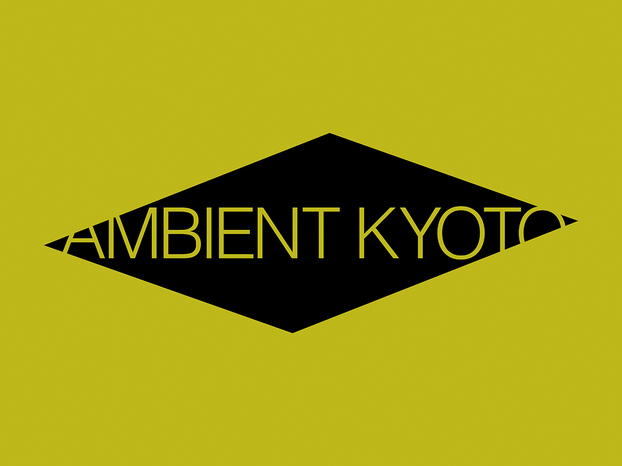
古都をいろどるアンビエントふたたび
スタンダードをラーガにみたてたとでもいえばいいか。テリー・ライリーの最新作『Terry Riley STANDARDⓈAND -Kobuchizawa Sessions #1-』は収録する全10曲のうち、6曲までがカヴァーですべてがスタンダード。詳細を記すと、ミュージカル分野に巨大な足跡を刻んだ作曲家、リチャード・ロジャースによる“Isn’t It Romantic?”や、ジェローム・カーンの手になる畢竟のスタンダードナンバー“Yesterdays”(1933年)など、出典はいずれも1920~50年代で、ライリーがみずからライナーノーツで述べるとおり〈アメリカン・ソングブック〉すなわち戦前のブロードウェイの舞台ないしミュージカル映画のスクリーンをいろどった楽曲の数々が中心となる。本作でライリーはこれらをふくむ全10曲のうち、アウトロの役割を担う“Gotcha Wakatcha”をのぞくすべての楽曲をピアノないしシンセの即興でうみだしたという。段取りきっかけもNGはむろんのことポストプロもクリックのたぐいもなく、まわしっぱなしのテープが去来する音のながれをとどめていく。即興といえば、私たちはつい既存の音楽の規則からに離れ、予測不可能な偶発性にいかに身をさらすかと語りがちだが、明確な形式と構造と方法をもつ音楽についても即興の余地は依然としてのこっている。とはいえそれは譜面のある作品における解釈可能性とも異なる、演奏する身体に固有の出来事であり、ジャズは長大な歴史をとおして、名演、凡演を問わず、それらをプールし、もって後代の導きの糸とも他山の石ともなした。スタンダードはその総称であるとともにソングにひそむ広大無辺さの別称でもある。
ライリーは本作でスタンダードに虚心坦懐にむきあっている。凝ったギミックはみあたらないが、さりとてこぢんまりとまとまるわけでもない。原曲をスタンダードにそだてあげたジャズの巨人たちへの敬意は演奏の端々ににじむものの、テクニックや名人芸を披露するわけでもない。悠揚かつ恬淡と、音と語り合うなかにライリーの即興にたいする思考がにじみだしてくる。
さきに私はスタンダードをラーガにみたてたと書いた。ライリーはジャズとともにインド音楽に傾倒し、盟友ラ・モテン・ヤングとその妻マリアン・ザジーラらとパンディット・プラン・ナートにながらく師事したのはつとに有名である。その成果と経過は1972年の『Persian Surgery Dervishes』をはじめいくつか作品に実をむすび、日本移住後の現在もライリーは月にいちど鎌倉でラーガの教室をひらいている。ラーガとはインド古典音楽の旋律面における基本的な理論で、メロディや装飾音に細やかな決まりごとがあり、ミュージシャンはそれに則って即興演奏をくりひろげる。いわば旋法と即興の枠組みでもあるが、つねに柔軟で可変性に富んでいる。即興におけるラーガの重要度は英国のギタリスト、デレク・ベイリーが各界の即興のあり方をたずねた著書「インプロヴィゼーション」の劈頭をインド音楽に割くことにもあきらかである。そこには、一説によれば、派生的なものをふくめると数万にものぼるというラーガと、それを培った悠久の歴史を、即興に資する語彙の人類史上最大の貯蔵庫とみなす著者の視点がほのめかされている。本稿ではそのことの可否は問わないが、インド音楽の即興のシステムが古典的な合理性を体現するとともに膨大な時間をストックすることに異論はない。そのような時間感覚はおそらくライリーの即興観に深く根づき、最新作におけるジャズのスタンダードの歴史性を照らしだす光源ともなろう。
旋律と即興の方法であるラーガが特定の季節や時間や情動に結びつくように、音楽はそれを奏でる〈場〉と無縁ではない。ここでいう〈場〉とは特定の場所を示すわけではないが、無色透明で匿名的な場所にとどまらない、あらゆる響きにひらかれた具体的な広がりをもつ空間としての〈場〉――そのような場をさして環境(アンビエント)と呼ぶことは可能か。
アンビエント・ミュージックの創始者ブライアン・イーノのアート作品を集成し、作家としての大系を提示した2022年の〈BRIAN ENO AMBIENT KYOTO〉は、主題のひとつであった自己生成=ジェネレーティブが本展の直後、生成AI分野で話題になるなど、作家の先見性をあらためて確認するともに、サウンドインスタレーション、オーディオビジュアルの進化と可能性を確認する恰好の機会ともなった。好評のうちに幕を引いた〈BRIAN ENO AMBIENT KYOTO〉からはや一年、その第二弾が〈AMBIENT KYOTO 2023〉として再帰する。