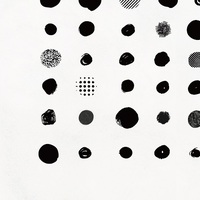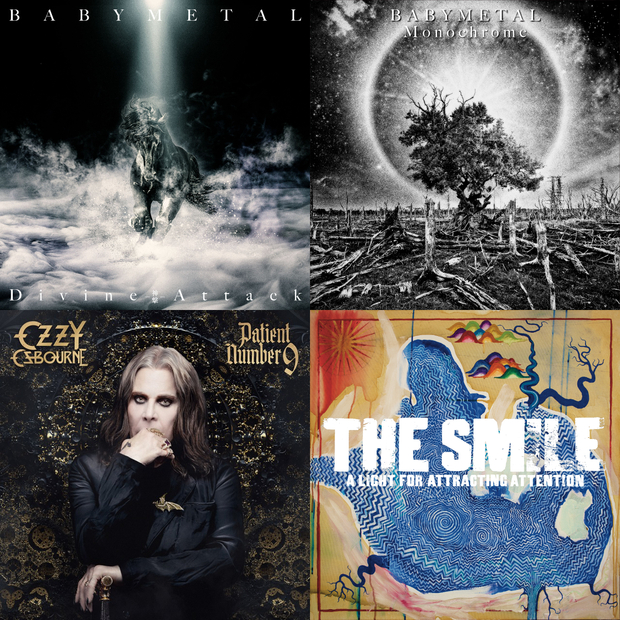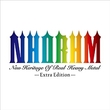『Dot』は不思議なアルバムだ。メタルに大きな影響を受けた作品とのことだが、アコースティック楽器のみからなるアンサンブルは肌理細かく洗練されていて、全体的な印象は欧州の仄暗いジャズやチェンバーロックに近い。しかし、各パートの動きや楽曲の構成に注目してみると、耳馴染みのよさとは対照的に奇妙な展開が多く、そこには確かにメタルならではの考え方も活かされていることがわかる。例えば、“Dot”終盤のミニマルな展開が、ECMとドゥームメタルを自然に融け合わせたようなサウンドになっていること。また、“Baroness”でハーフタイムを連発するリズムアレンジが、メタルコアのブレイクダウンにも通ずること。
こうした音楽性は、近年増えてきたメタル影響下のジャズと似た質感を持ちながらも、成り立ちの面では大きく異なっているように思う。ティグラン・ハマシアンやキャメロン・グレイヴスがメシュガーやジェントの系譜に大きな影響を受けているのに対し、西山瞳は伝統的なハードロック/ヘヴィメタルから出発し、それ以降のメタルの要素も新たに学び取り入れている。このような経路をたどって築き上げられた音楽は、世界的にみても稀ではないだろうか。60年代のマイルス・デイヴィスなどを楽しむ感覚で浸ることもできるが、内部構造は特異で、センスオブワンダーをもって聴き込むほどに面白みが増していく。
今回のインタビューでは、以上のような音楽性についての興味深い話をたくさん聞くことができた。この素晴らしいアルバムを理解するにあたっての手がかりになれば幸いだ。
メタルのように全員でゆっくり紡いでいくエネルギー
――いただいたコンセプト資料、すごく興味深かったです。今日はそちらをふまえてお話を伺えればと思います。まず、今回のアルバムはメタルの影響が大きいとのことですが、具体的にはどういった類のメタルを意識されたのでしょうか。
「意識したのは、メタルの中の何かのジャンルというよりも、ストリームの作り方や質感のほうですね。ジャズだともう少し刹那的にことが進んでいって、結果として何かができるようなところがあるんですけど、それとは違って、潮が満ちていくような感じ、全員でゆっくり同じことを紡いでいくようなエネルギーを意識しました。
最近、メタルもそうなんですけど、自分の意識がバチッと変わるきっかけになったのが、やっとレディオヘッドが聴けるようになったことなんですよ。私はすごく映画好きなので、コロナ前まではわりと映画館に行ってたんですけど、好きな映画の好きな劇伴を担当していたのがジョニー・グリーンウッド(レディオヘッドのギタリスト)だったんですよね。それを知った上で、彼やレディオヘッドのアルバムを聴いたら、私が苦手だったのはトム・ヨーク成分だったんじゃないかと気付いたんです(笑)。それでジョニー・グリーンウッドを掘り下げて聴いていって。
それと並行して、最近のメタルコアバンド、コード・オレンジなどを聴くようになったら、わりと楽しめるようになったんですね。そして、それが90年代当時は自分が嫌いだったグランジみたいな音楽からちゃんと繋がってることもわかって。それでいろんなものが聴けるようになったところがあります。コーンとかすっごい嫌いだったんですけど(笑)、そういう当時は敵視してたものを全部聴きなおしていきました。
なので、今回のアルバムについて言うと、自分が昔から好きだったものよりは、そうでないものの質感、インダストリアルっぽいものなどに興味が湧いたのが大きかったかもしれないです」
――90年代当時はインダストリアルやグランジ系が大嫌いだったとのことですが、その理由はご自身で分析されていますか。
「なんかね、景気が悪いという感じがして(笑)。私自身がずっとピアノを真面目に練習してきたこともあって、テクニカルなものを聴いてわっと驚き楽しむようなところもあったから。(インダストリアルやグランジには)それがないな、なんでやねん!みたいな(笑)」
――〈景気が悪い〉というのは、HR/HM(ハードロック/ヘヴィメタル)とニューメタルなどを分かつものとして、とてもよく核心をついている表現だと思います。
「なんか、(サウンドが)疲れてそうだったんですよね(笑)。あと、グルーヴの質的にも、ルーズに聞こえていたのが当時は好きじゃなかったんでしょうね」
――はい。それで、今回のアルバムにはそういったエッセンスも入っているということでしょうか。
「そうですね。“Tidal”などではそういうルーズさを意識しました。それから、レディオヘッドを聴けるようになったこともあって、フォークソングみたいなものからの影響もあります。“Red and Yellow”とかがその例ですね」