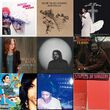女王の指定席はいつもてっぺんにある。才能に苦心を掛け合わせて下町から這い上がったバーバラがバーブラになった時、アメリカン・ショウビズの覇権は彼女に委ねられた。歌手、女優、監督、作曲家、プロデューサー、オピニオン・リーダー、努力家、ロマンティスト、天才、野心家、バーブラ・ストライサンド。シーンの最前線で歌い続けて60年。彼女の椅子はいつも頂上にあるが、その優雅で愛と慈しみに満ちた歌声はいつでも我々の側に降りてくるのだ。

10月4日付のビルボード誌にて総合チャートを制したのは、バーブラ・ストライサンドのデュエット・アルバム『Partners』――彼女にとっては『Love Is The Answer』(2009年)以来の全米首位となり、これによって彼女は1960年代、70年代、80年代、90年代、2000年代、2010年代にそれぞれNo.1ヒットを残したことになった。6つのディケイドを制したアーティストは全米チャート史上において、もちろん唯一無二である。

そういったチャートの意味やセールスの大きさが即ち作品そのものの価値に結び付くものではないとはいえ、少なくともバーブラがいかに長く愛され続けているか、そしてそれがいかに難しいことか、ということは単純にわかるだろう。一口に〈国民的スター〉と形容すればいいポジションではあるのだろうが、芸能がそのまま芸術として愛されうる国での〈国民的スター〉はまたニュアンスが違う。同じ42年生まれのアーティストではポール・マッカートニーやカエターノ・ヴェローゾ、アレサ・フランクリンらも現役だが、そういったレジェンドたちの〈レジェンドたる由縁のわかりやすさ〉に比べて、バーブラの凄さというのは少しわかりにくいのかもしれない。ただ、例えばマイク・マイヤーズによる90年代の「サタデー・ナイト・ライヴ」での馬鹿馬鹿しいコントや、ダック・ソースのノヴェルティー・ヒット“Barbra Streisand”における〈調理〉のされ方からしても、彼女という〈素材〉に対する理解が本国では一般的な共通認識として広まっていることがよくわかる。
どこにでもいそうな感じの子
〈バーブラ・ストライサンドは上品ぶったことなんかないわ〉〈どこにでもいそうな感じの子〉〈いつも言っていたそうよ、自分はビッグになるって〉〈特別な生まれじゃなかった。父親は教師で、母親も普通の主婦〉〈私の友達は、彼女の歌を聴くためだけに窓を開けていたんだって〉――故郷を主題とする2012年のツアーから凱旋公演の模様を収めたライヴ盤『Back To Brooklyn』の導入部には、ブルックリンの人々が地元のスターへの思いを語るコメントが演出としてインサートされている。バーバラ・ジョアン・ストライサンドはNYのウィリアムズバーグでユダヤ系の一家に生まれた。生後すぐにブルックリンへ引っ越した彼女は、夢を追って飛び出すまでそこで育ったが、教師だった父親は彼女が1歳の時に亡くなり、決して恵まれた環境ではなかったようだ。早くからショウビジネスの世界に憧れ、「暮らしていたアパートのロビーは音の反響がとても美しく、自分がいい声を持っていると初めて気付いたのもそこだった」という本人の回想からは夢中で歌う少女の姿も浮かんでくるが、彼女と継父の関係は良いものではなく、母親は娘の将来を後押しすることはなかったという。
進学したエラスムス・ホール高校では合唱部に属していたが、彼女が初めてのデモを録音したのはそれに先駆けた13歳の時。女優志望でオフ・オフ・ブロードウェイの舞台に立ちながら、高校を出てからはナイトクラブで歌っていたそうだ。その前後、60年頃には個性を求めて名前をバーバラ(Barbara)からバーブラ(Barbra)に改めている。
そんな名前の引っ掛かりも効果を発揮したのか、62年にはミュージカル「あなたには卸値で」にてブロードウェイに進出。コロムビアとレコード契約を結び、翌年のファースト・アルバム『The Barbra Streisand Album』はいきなりグラミーで2部門を受賞した。64年にはジュール・スタイン&ボブ・メリルの音楽によるミュージカル「ファニー・ガール」での主演が当たり役となり、そこでの歌唱曲などを収めた4枚目のアルバム『People』は初めて全米1位を獲得している。ビートルズを筆頭とする〈ブリティッシュ・インヴェイジョン〉の熱波が全米を襲ったのと同時期ながら、バーブラが60年代に発表したアルバムは軒並みゴールド・ヒットを記録。アダルト・コンテンポラリー層を中心に、新進のポピュラー歌手として人気を早くも盤石にしたのだった。ちなみに、63年に結婚した俳優エリオット・グールドとの間に一粒種のジェイソンを授かったのも66年のことだ。
てな感じに急ぎ足でまとめていくと順風満帆でしかないキャリアのようにも映る。だが……政治的な態度を明確にしていたバーブラにはやがて脅迫が相次ぐようになり、67年には恐怖からツアーやライヴを行わなくなってしまった。前後して、映画化された「ファニー・ガール」(68年)を皮切りに演技の場もスクリーンに移行。それから約30年もの間、バーブラと大衆のコミュニケーションはレコードと映画のみに限られることとなった。このことがオーディエンスの渇望を煽り、彼女の超然とした大物感を形成していった部分も(結果的には)あるのかもしれない。
ショウビズ界の頂点で
ミュージカルやナイトクラブを成り立ちとするポピュラー・スタンダード方面に素養の確かさを見せたのが60年代のバーブラだとしたら、70年代はコンテンポラリーなロック/ポップス路線を模索しつつ女優としてのステイタスも活かしながら支持層を広げた時期ということになるだろうか。背景には当時のレーベル代表だったクライヴ・デイヴィスの意向も大きかったようだが、ともかく私生活では離婚も経験した71年、ローラ・ニーロ曲を表題に取り上げた『Stoney End』(リチャード・ペリーのプロデュース)のプラチナム・ヒットによって、路線変更は上々の滑り出しをみせている。この時期には映画「追憶」(73年)の主題歌とそれを含むアルバム『The Way We Were』(74年)が全米No.1を獲得し、製作総指揮も手掛けた「スター誕生」(76年)のテーマであるバーブラ作曲の“Evergreen”(77年)がまたも全米を制覇。その後も高校の先輩ニール・ダイアモンドとの“You Don't Bring Me Flowers”(78年)、ドナ・サマーとの異色デュオによるディスコ・ナンバー“No More Tears(Enough Is Enough)”(79年)、そしてビー・ジーズで絶頂を極めていたバリー・ギブの手による“Woman In Love”(80年)がいずれも全米チャートNo.1に君臨し、この時期のバーブラは他のどの時代よりもシングル・ヒットに傾注していたと言える。

アルバム制作のほうも西海岸の活況に乗って後の大物たるデヴィッド・フォスターら多様なブレーンを柔軟に起用し、また違う角度から楽しめそうなフュージョン/AORマナーの名品も数多い。なかでも先述のバリー・ギブと全編で手を組んだ『Guilty』(80年)はキャリア最大のヒット・アルバムに。こうした商業的な成功を以て、当時の彼女は〈USでもっとも成功した女性シンガー〉と認められるに至っている。そのように後進アーティストたちと競って流行に挑みながら賑やかに突入した80年代ではあったが、そこでバーブラが選んだ一手は、意外にも原点であるミュージカル的な作風への回帰を示すものだった。当然のようにレーベルは猛反対したらしいが、この選択が結果的に彼女のその後30年に大きな輝きを与えたことは疑いない。
そうして完成した『The Broadway Album』(85年)は全米チャートの首位を3週守り、予想以上の成功と高い評価をバーブラにもたらした。80年代らしさを謳歌した多くの大物スターたちが90年代を目前に方向性を見失っていくなか、伝統的なショウ・チューンの魅力を伝えるアルバム・アーティストにふたたび立ち戻った彼女はそのレースからいち早く離脱していたというわけだ。
そんなポジショニングが音楽活動にかつてないマイペースを許可することがあったとしても、彼女は2本目の監督作品となる映画「サウス・キャロライナ 愛と追憶の彼方」(91年)に取り組み、また民主党支持の立場から政治活動との関わりに時間を費やしていた。バーブラの影響力はすでにエンターテイメント業界に止まらないパワーを発揮するほどに高まっていたのである。それでも念願叶ってビル・クリントンが大統領に就任した93年には、ヒット企画の続編的な『Back To Broadway』をリリース。これをまたしても全米チャートの頂上に送り込み、27年ぶりのコンサート・ツアー開催も発表。本国のメディアを大いに騒がせたこのカムバックはすぐにチケットがソールドアウトする事態となり、ライヴ・パフォーマーとしての己の価値を広く世に知らしめることとなった。
ありのままの
97年にはアリフ・マーディンやウォルター・アファナシエフをプロデュース陣に迎えた『Higher Ground』をリリース。セリーヌ・ディオンらマライア・キャリーに通じるディーヴァ性をコンテンポラリーに表現し、これまた全米No.1を獲得。その合間には、監督/主演を務めた映画「マンハッタン・ラプソディ」(96年)の主題歌としてブライアン・アダムスと共演した“I Finally Find Someone”や、セリーヌ・ディオンとのコラボ“Tell HIm”といった後進とのヒットも生み出している。98年には俳優のジェームズ・ブローリンと2度目の結婚をし、その関係をみずから祝福するような『A Love Like Ours』(99年)をリリース。その後は〈Timeless〉と題されたコンサートにてステージに再復帰し、なかでもラスヴェガス公演は同地における単独歌手のコンサートとしては過去最大級の収益を上げることに成功した。
ライヴ活動を停止して臨んだ2000年代には、オーケストラを従えて映画のテーマ曲縛りで挑んだ『The Movie Album』(2003年)、『Guilty』の続編としてバリー・ギブと再会した『Guilty Pleasures』(2005年)など過去の遺産をアップデートするような良品を断続的にリリースし、2006年には6年ぶりのコンサート・ツアーも行った。それに絡んだMSGのコンサートではブッシュ大統領をコキ下ろす寸劇を披露し、野次を飛ばしてきた観客に怒鳴り返すという事案も発生しているが、政治や環境問題、女性やLBGTの地位向上にまつわる運動まで、多様な活動におけるオピニオン・リーダー的なポジションを担いながらも、変にかしこまらず思いのままに振る舞う率直さがまた支持を得る部分でもあるのだろう。コンプレックスだったとされる鼻を整形せずに〈ありのまま〉で成功を収めた姿勢が、セクシャル・マイノリティーの心に救いを与え、「glee/グリー」で自己肯定の象徴のように崇められるのもよくわかる。そしてもちろん、その根源となるのは、ジャズもソウルもカントリーも包容するようにヴァーサタイルで圧倒的なヴォーカルだ。シンプルなことだが、どんな数字や勲章にも置き換えられない彼女の魅力は、ブルックリンのアパートで歌っていた頃から変わっていないのかもしれない。
▼関連作品
左から、ニール・ダイアモンドのベスト盤『The Essential Neil Diamond』(Legacy)、ビー・ジーズのベスト盤『The Ultimate Bee Gees』(Rhino)
※ジャケットをクリックするとTOWER RECORDS ONLINEにジャンプ
▼バーブラ・ストライサンドの作品
左から、2013年のライヴ盤『Back To Brooklyn』、2枚組のベスト盤『The Essential Barbra Streisand』、自選の未発表音源集『Release Me』(すべてColumbia)
※ジャケットをクリックするとTOWER RECORDS ONLINEにジャンプ