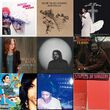【PEOPLE TREE】
エレクトリック・ライト・オーケストラ
ロックンロールをシンフォニックに表現してみよう、きっとそこには誰もまだ見たことのない魔法のような世界が広がっているはずだから――希望を胸に、エレクトリック・ライト・オーケストラは飛び立った。あれから45年。ジェフ・リンの描く煌びやかな光は、いまなお私たちを虜にし続ける。しばしの休息を挿み、大いなるコスモスをめざして離陸のサインが点灯しはじめた。夢の時間はまだ終わらない……
★Pt.1 コラム〈ELO/ジェフ・リンの足跡〉はこちら
★Pt.2 コラム〈ELOサウンドの構成要素/ロイ・ウッド〉はこちら
★Pt.3 ディスクガイド〈ELOを知るための10枚〉はこちら
★Pt.4 ディスクガイド〈ELOをめぐる音楽の果実〉はこちら
THE WORLD SHINES FOR ME TODAY!
レジェンドたちの再起を手助けした、プロデューサーとしての手腕
ジェフ・リンが他者のプロデュースを精力的に行うようになったのは80年代半ばからだが、裏方としての名声を確立したのはジョージ・ハリスンの87年作『Cloud Nine』を発端とするトラヴェリング・ウィルベリーズ人脈――トム・ペティの89年作『Full Moon Fever』やロイ・オービソンの89年作『Mystery Girl』――を手掛けたあたりから。この一連の仕事において〈ジェフ節〉とも言うべきサウンドが、広く世に認知されたことは間違いない。その特徴は、ギターやヴォーカルの重ね録りによって厚みを増した、奥行きのあるジェフ流のウォール・オブ・サウンドと、独特のエフェクト処理によってバシャンバシャンと乾いた音を鳴らす、どこか遠くから聴こえてくるような(60年代風とも言える!?)ドラムスにある。
そんなジェフの個性の強さは、ランディ・ニューマンの88年作『Land Of Dreams』やブライアン・ウィルソンの88年作『Brian Wilson』などで、彼の関与したナンバーと他の収録曲に一聴して明確なカラーの違いがあることでも実証済みだ。そのため、時にオーヴァー・プロデュースと非難されることもあったが、ジョージやロイはもとより、デル・シャノンの91年作『Rock On!』にジョー・ウォルシュの2012年作『Analog Man』、ブライアン・アダムスの2015年作『Get Up』など、一定のブランクを経たヴェテランの復活作(にして成功作)を数多く手掛けてきた例を踏まえれば、ジェフの鮮烈な音作りが従来のアーティスト像を刷新し、新たなフェイズへと導くためのカンフル剤的な役割を果たしているように思えてならない。また、シンプルなロックンロールを最新のテクノロジーでもってモダン化する手腕も見事ながら、完成したサウンドにはどこか英国人らしい繊細さと実直さ、そして憧憬と畏敬に溢れたピュアネスを常に感じる。そこには確かにジェフの人柄が滲み出ているし、だからこそ彼の仕事はどれもたまらなく魅力的なのだ。