〈未聴〉の領域を手繰る、作曲家の手仕事。
『音の始源を求めて』と題されたCDシリーズがある。列島でつくられた電子音楽を扱い、おそらく、1990年ころからのリリースと記憶する。本誌でも紹介がおこなわれた。


1作目からはすでに30年以上になるが、最近、作家シリーズとして、湯浅譲二の11、一柳慧の12が日をみた。湯浅作品は高名な“イコン”“ヴォイセズ・カミング”を含む6作、一柳作品(2枚組)は“東京1969”“ミュージック・フォー・リヴィング・スペース”とともに、50分をこえる大作“空(Kū)”を含む5作、どれも1960年代から70年代にかけての電子音楽作品である。
湯浅譲二は、〈未聴〉ということばをよくつかう。この作曲家にとって、電子音楽は、まさに〈未聴〉を招き寄せ、作品化するものであり、そうした得たもの、考えたものが楽器の作品へと応用されることも多い。ジョン・ケージとともに活動した一柳慧――昨2022年に亡くなられた――は、ひとつの固定した作品をつくるにしても、偶然的なことどもがかかわってくること、さらに空間や環境への関心を生かそうとした。時期的にかさなるし、CDというメディアをとおしてひびいてくるものにつながるものがあるにしても、それぞれの作品が発想され、音として発された場を想像すると、かなりの隔たりが浮かびあがってもくる。
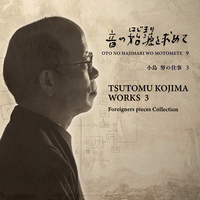
VARIOUS ARTISTS 『音の始源を求めて 9 小島努の仕事 3[FOREIGNERS PIECES COLLECTION]』 サウンドスリー(2023)
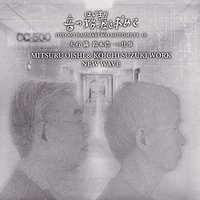
これら2枚の前にも従来のエンジニア・シリーズとして『9 小島努の仕事 3』『10 大石満・鈴木浩一の仕事』がシリーズにはある。これらは1970年代後半から80年代の作品を収録。前者にはエロワ“楽の道”が、後者には近藤譲“リヴァラン”が収録されていて――この2曲、40数年前、作曲家がひとつひとつの音を聴きなおしコメントする姿をみかけ、感慨をおぼえたことをおもいだす。個人的なことだけれども。
作曲家は、あたまのなか、どこから、どんなふうに音がしてくるかをイメージする。するのだろう、とおもう。生身の演奏家がいるなら、どの楽器をどこに、というようなことを考える。演奏される場所についても、だ。電子音楽の場合はどうか。楽器を奏でる演奏家がいるときより、作曲家は音をききながら、つくりこむ。演奏家や会場によるほどは、スピーカーを前にした作曲家は、違いを感じない、のかどうか。そんなことをつらつらとおもいつつ、もともとスピーカーからでる音にふれる電子音楽は、楽器をそのときその場で演奏するものより、作曲家が求めているものとの隔たりは少ないか?、と問いは堂々めぐり。すべての音響装置が空間的に調整されているのとは違うかもしれないけれど、とも。


































