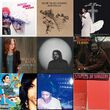キャリアの長いグループこそ数あれど、常に第一線に立ってここまでコンスタントに活動しているブランドもそう存在しないだろう。中心人物を何度となく失いながら、時代の息吹を吸って変化を繰り返し、それでも紳士的なマナーを纏ってソウルの帝王であり続けるテンプテーションズ。この帝政に終わりはない
ヴォーカル・グループは星の数ほど存在するが、60年近くに及ぶ活動歴の長さも含めてテンプテーションズほどの絶対的王者はいない。まずはそう断言してしまおう。ソウル・ミュージックの範疇に留まらず、アメリカのポップ音楽界を代表する存在としてテンプスという略称でも親しまれてきた5人組。60年代後半に共演アルバムを吹き込んだシュープリームスと並ぶモータウンの看板グループで、ファンク・ブラザーズのロバート・ホワイトによるギター・リフに導かれて歌い出す64年の全米No.1ソング“My Girl”はレーベルを代表する一曲としても名高い。長い歴史の中でメンバーは頻繁に入れ替わったが、その都度、歌とダンスに長けた美男や紳士を補充し、クィンテットというフォーメーションを保ち続けてきた。
今年2月には、60年代末からのメイン・リードで、ソロで活躍した80年代に“Don't Look Any Further”(84年)などのヒットを放ったデニス・エドワーズが74歳で他界。デニスはテンプスを離れた90年代から〈テンプテーションズ・レヴュー〉という分派グループを率い、近年まで頻繁に来日もしていたが、ここで言うテンプテーションズとはオーティス・ウィリアムズ率いる本家のほう。

そんな彼らが8年ぶりに新作『All The Time』を発表した。内容は、サム・スミス、ウィークエンド、ブルーノ・マーズ、エド・シーラン、マックスウェル、ジョン・メイヤー、マイケル・ジャクソンのヒット曲カヴァーに3曲のオリジナルを加えたもので、カヴァーした曲の歌い手と世代は違えど、かつてはテンプスもポップ・ミュージック界を賑わすアイドルだったことを仄めかす。一方オリジナルは、分厚いハーモニーで迫るバラッドの先行曲“Waitin' On You”やモダンなステッパー“Be My Wife”などソウル/R&Bとしての濃さを失わず、ブラック・コミュニティーに寄り添い続ける彼らの良心を見る思いだ。
誘惑のハーモニー
「安住するより冒険を好んだグループだった」と語っていたのはリーダーのオーティス・ウィリアムズ。つまりメンバー交代と新しいサウンドの導入を繰り返してきたわけだが、唯一変わらないのが5人であること。グループ内での役割もはっきりしていて、ファルセットを用いるハイテナーと低い声のベースという高低のパートふたりと、その中間のテナーとバリトンを担当するのが3人。そんな5声によるハーモニーの接着剤的な役割を務めてきたのがオーティスで、ミシガン州デトロイトにてメルヴィン・フランクリン、エルブリッジ・ブライアントらと組んでいたディスタンツが、脱退したメンバーの穴を埋めるべくプライムスとして活動していたアラバマ出身のエディ・ケンドリックスとポール・ウィリアムズを迎え入れたことがグループの始まりとなる。モータウン設立間もない60年前後のことだ。
ディスタンツの名前が権利関係で使えなくなり、エルジンズと名乗るも同名グループの存在を知ってテンプテーションズと改名した彼らは、61年に地元のミラクルからサム・クック調の“Oh, Mother Of Mine”などを発表。62年にはモータウン傍系のゴーディから出した“Dream Come True”がR&Bチャート22位のヒットを記録するが、人気がいまひとつだったこともあって、モータウン傍系のメロディからパイレーツ名義でシングルを出すなど試行錯誤が続いた。この頃の看板リードはハイテナーのエディとバリトンのポールのふたりだった。
そんな彼らに転機が訪れたのが63年12月。アルコール依存でクビになったエルブリッジの代わりにオーティスのご近所仲間だったデヴィッド・ラフィンが加わったことがグループを大きく動かす。リーゼントに黒縁メガネという出で立ちで派手なアクションを交えて荒々しい歌を聴かせるデヴィッドは、艶やかなファルセットを放つエディと共にグループの看板に。このふたりのほか、愛嬌のあるキャラでベース・ヴォイスを担当したメルヴィン、力強い歌に加えてダンスの振り付けにも才能を発揮したポール、ハーモニーのカギを握ったオーティスが、後にファンが認める〈黄金期の5人〉としてテンプテーションズというブランドを確立した。
ブレイクとなったのは、64年にキャッシュ・ボックスのR&Bチャートで1位に輝いたスモーキー・ロビンソン制作の“The Way You Do The Things You Do”。エディのファルセットを含めてインプレッションズを手本にしたというこれや“My Girl”は、後年にかけてのトレードマークとなるテンプスのヴォーカル作法が集約されていた。米深南部出身でゴスペルに親しんできたメンバーの出自を伝えるような古式ゆかしさとディープネス。そして、北部移住後に虜になったというドゥワップの都会的洗練とポップネス。特にフラミンゴスは彼らのアイドルだったようだが、深く息を吐き出して厚みを出すブロウ・ハーモニーはムーングロウズから学んだという。同時に、女性を中心とした若いファンを持つアイドルでもあったテンプスはダンスにも力を注いでいた。デヴィッドのニー・ドロップ(膝落とし)も有名だが、グループの激しくも上品なダンスは主にポールの振り付けで、名振付師のチョリー・アトキンスにも厳しい指導を仰ぎながら完成させたと言われている。
常にセクシーで洗練された紳士であることを心掛けていた彼らはメンバーの身長やスタイルにも厳しく、例えば以前デヴィッドと一緒にテンプスのオーディションに来た兄のジミー・ラフィンは、オーティスいわく「ダンスが下手そうで不格好だったから採用しなかった」という。また、80年代にキャピトルからのソロ作で人気を集めるボー・ウィリアムズは、歌の実力を買われてオーディションに出向くも身長が加入規定に満たず不採用となっている。グループ名を〈誘惑〉とした彼らにとって、歌だけでなく見栄えも重要だったのだ。
〈エディの歌を聴いて下着を濡らすような女の子のために曲を作る〉——仲間内ではそんな会話もなされていたようだが、誘惑されたのは女性ファンだけではない。85年にホール&オーツとしてNYのアポロ・シアターでデヴィッドとエディを迎え、ライヴを行ったダリル・ホールが活動初期にテンプスに憧れてテンプトーンズというグループを組んでいたことはよく知られている。また、後にデトロイトから同じ5人組のヴォーカル・グループとしてドラマティックス(劇的)やエンチャントメント(魅惑)が登場したのも、地元の先輩であるテンプスへの憧れが高じてのことだろう。
こうして彼らは66年にR&B No.1ヒットとなった“Get Ready”まで、主にスモーキー・ロビンソンとのタッグでヒットを連発。一方で、そんな活躍を横目で見ながら密かに裏方のポジションを狙い、その座を勝ち取ったのが、以前ディスタンツのメンバーと同じ高校に通っていた鬼才ノーマン・ホイットフィールドだった。ノーマンはデヴィッドの荒くれた魅力を前面に押し出した“Ain't Too Proud To Beg”(66年)などで彼らをさらなる高みに導き、グループ屈指のラヴ・バラードとなる“I Wish It Would Rain”(67年)も献上している。が、この頃エゴを剥き出しにしていたデヴィッドの無頼漢ぶりが頂点に達し、メンバーはデヴィッドをグループから追放。その後ソロとしての道を歩みはじめるデヴィッドの後釜として68年に加入したのがデニス・エドワーズだった。
アラバマ出身の彼もゴスペルを基盤とする粗削りで野生的なシンガーだが、デヴィッドとはまた違ったストイックな熱さは〈ブラック・パワー〉が叫ばれる時代の風潮とグループの新機軸にマッチ。オーティスの勧めでスライ&ザ・ファミリー・ストーンの“Dance To The Music”を聴いたノーマンが同曲に刺激されて制作した“Cloud Nine”(68年)が大ヒットとなり、〈サイケデリック・ソウル〉と呼ばれる激しくファンキーな曲がテンプスの新たなスタイルとして定着する。また、社会的・政治的に揺れていた当時の世相を反映して、ベトナム戦争の帰還兵から聴いた話をもとに書かれた“Ball Of Confusion(That's What The World Is Today)”(70年)のようなメッセージ~プロテスト・ソングを歌うことも増え、マーヴィン・ゲイやスティーヴィ・ワンダーらと共にニュー・ソウル運動の気運を盛り上げていく。72年に大ヒットとなったファンキーでシリアスな“Papa Was A Rolling Stone”はその象徴と言っていいだろう。
名門の誇りにかけて
ただ、チャート的には絶好調でありながら、71年のバラード“Just My Imagination(Running Away With Me)”の録音直後、リードを歌っていたエディがグループと距離を置きはじめ、ソロに転向。同年には鬱病とアルコール依存に悩んでいたポールも脱退し(73年に自殺)、その穴を元ディスタンツのリチャード・ストリートが埋め、エディのパートもデイモン・ハリスが受け継ぐなど、グループの内部は混乱していた。また、ノーマンとの蜜月もノーマンが自身のホイットフィールドを設立した73年あたりで終わりを迎えており、その後はR&Bチャートで健闘するもポップ・チャートでは低迷。77年にはデニスも脱退し、モータウンからも離脱する。
こうしてルイス・プライスを加えたテンプスはアトランティックに新天地を求め、デイモンの後釜となったグレン・レナードが以前トゥルー・リフレクションで録音経験のあったフィラデルフィアにてアルバムを制作する。ただ、彼らがフィリー・サウンドと相性が良かったことは、80年代突入と同時にモータウン(ゴーディ)に戻り、デニスも復帰してトム・ベルと組んだ81年のセルフ・タイトル作を聴いても明らかだ。
82年にデヴィッドとエディを一時的に呼び戻し、〈リユニオン〉を謳ったアルバムとツアーを成功させたことは、3度目の大きなターニング・ポイントとなった。この時だけは例外的に7人編成となったが、リック・ジェイムズが新しいファンクのスタイルを持ち込んで制作/客演した“Standing On The Top”が6年ぶりにR&BチャートのTOP10圏内に入り、ふたたび最前線に復帰。グレンの後釜となるハイテナーとして元エシックス~ラヴ・コミッティのロン・タイソン、そしてソロに転向したデニスの後継者として旧メンバーよりひと回り年下のアリ・オリ・ウッドソンが加入したのはこの後のことだ。特にアリ・オリの若さや突進力が全開となるダンサー“Treat Her Like A Lady”(84年)は好評を博し、以降はデニスの一時再復帰もありながら、稀代の熱血シャウターであるアリ・オリをフロントに据えて“Lady Soul”(86年)や“Special”(89年)といった深い色気の滲むバラッドやスロウ・ジャムでマチュアーなヴォーカル・グループとしての粋を見せていく。思えば、デヴィッド、デニス、アリ・オリが加入するタイミングでサウンドが変化し、新たなフェーズに突入しているあたり、テンプスの魅力は荒々しいシャウターの雄々しさに負うところが大きかったのだろう。
かつての二枚看板だったデヴィッド(91年没)とエディ(92年没)が相次いで世を去り、メルヴィンの他界(95年)前後にはセオ・ピープルズの加入やアリ・オリの脱退など出入りが激しくなるが、この20年近くはオーティスとロン、元フォー・ラヴァーズ・オンリーのテリー・ウィークスの3人が不動で、残りの2席を名門グループ出身者などが奪い合ってきた。モータウンからは2004年作『Legacy』を最後に離れるも、以降は自分たちの存在意義を確かめるかのように、〈最前線に復帰〉〈不死鳥復活〉〈まだここにいる〉などといった意味のタイトルを冠し、名門の誇りにかけて現行シーンとも向き合いながら良作を出し続けている。
94年に出された5枚組アンソロジー『Emperors Of Soul』のタイトル=〈ソウルの帝王たち〉は89年に〈ロックンロールの殿堂〉入りを果たした時に授けられた称号だが、それから30年近くを経た現在、数々のヴォーカル・グループが生まれては消えていくなかで帝国を守り抜いているテンプスは帝王以外の何者でもない。5つ星のソウル紳士たちは、いまもリスナーを誘惑し続けているのだ。 *林 剛
『All The Time』で取り上げた楽曲のオリジナルを収めた作品を一部紹介。