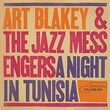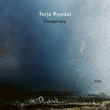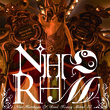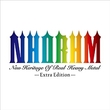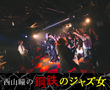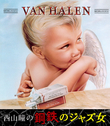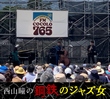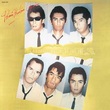ロック小僧だから太鼓を遠くに置きたい!
――ジャズドラムを始めて、ロックと違って苦労されたことはどんな部分でしたか?
「バスドラムの踏み方、音色、チューニングも、全然違うよね。自分の演奏を録音して聴くとバランスが悪かったりとか、欠点やマイナス要素を見つけて、少しでもエルヴィンとかのああいう感じのサウンドになればと、自分なりに考えてやっていった。ビデオテープが擦り切れるまでドラマーの演奏を繰り返し観て、フォームを真似したり、前屈みになってみたり、奏法を真似して。体格も身長も違うけど、工夫してね。ドラムセットも、昔のグレッチのビンテージのセットを使ったりして。
この頃のコージー(のバスドラムのヘッド)は24インチ。バスドラムはでかいものだと思っていたから、ジャズで使う18インチとか、最初は〈ええっ!〉と思ったもん。シンバルも、元々使っていたパイステの煌びやかな固めのだとサウンドがバンドの演奏に混じらないから、ジルジャンとかのジャズ系で使うような古いのに変えて。スティックも細いのに変えたり、一点ずつ全部違うのよね」
――今、鬼怒無月さん(ギター)とされているセッションは、ジャズセットでやってるんですか?
「鬼怒さんとのロックセッションは、ロックセット。それは、そういうサウンドが欲しいから。
ジャズドラムで培った要素は全く取り入れていないわけじゃなくて、バスドラムのチューニングもタイトにせずに、サステインがある感じの、ジャズっぽく鳴りすぎない感じではやってたりするかな」
――そもそもの話なんですが、江藤さんは今のご自分をジャズドラマーと思っていらっしゃるんですか?
「全然思ってないね、うん、思ってない。あんまり決めてないっていうか、昔から決めるのは好きじゃないんだけど。ちゃんとジャズをやった方がいいのかね(笑)」
――ロックをやっていたことで、現在のジャズのプレイに活かされていることってありますか?
「やっぱり安定感とかパワー感とか、音のビジョンはロックで身に付けたものじゃないかな。音の引き出し方っていうのは表面的なところだけじゃなくて、音の厚みとか幅とか、楽器全体をポーンって鳴らすことだから。スピード、パワー、音量、あと、ロックはドラムが凄く安定してないとダメじゃない。
あとね、ロック小僧だから、ドラムセットのそれぞれの太鼓を遠くに置くのが好きなの」
――ああ、なるほど!
「わかるやろ? 可能な限り遠くに置きたい。もちろん見た目の格好良さもあるけど、全部簡単な近いところにあると、スケール感も小さくなるし、面白くないの。遠くに置くと、オーバーアクションで叩くことになって、打つまでに少しタイムラグがあるわけ。だから、音の溜めができる気がする。そういうのが好きみたい。
あと、距離があると、音が分離して気持ち良いの。ぐしゃっとならず音が広がって、スケールが大きくなる。でも、離して四方に配置してある分、手首のグリップとかきちっとしてないと、叩けない」
――ジーン・クルーパとかは、どんな感じだったんでしょうね。見せ物としてのドラムセットが彼の頃から始まってるわけですよね。
「あの辺のセットも、実際叩いたら結構ダイナミックになる配置なんじゃないかな。特に1930年代、40年代の映像や写真を見たら、バスドラムも大きいじゃない。30インチぐらいあったりするから」
――ジーン・クルーパ、バディ・リッチ、ルイ・ベルソンなど、初期のジャズドラマーの名前は、ロックをやっていた時に知ってましたか?
「名前ぐらいは知ってた。やっぱりその辺の人たちの憧れでもあるから、興味はあったんよね。
例えば、コージーのレインボーでやってた頃のドラムソロには、ルイ・ベルソンのドラムソロをそのままロックドラムに置き換えたのとかがあるからね。デューク・エリントンの“Skin Deep”かな、あの辺のソロを、ロック風にツーバスに置き換えて引用してるのもあって」
――コージーはルイ・ベルソンが好きだったんですか。
「好きだったみたい。ツーバスを使うことに関しても影響を受けたんじゃないかな。もちろんジンジャー・ベイカーもそうだけど」
――ルイ・ベルソンって変なセッティングでしたよね。
「そうそう。まあ、ほとんどショーアップのためって感じもあるし。
例えばマックス・ローチの『Drums Unlimited(限りなきドラム)』(66年)ってアルバムがあって、ドラムソロの曲があるんだけど、ジョン・ボーナムがここから沢山引用してるんだよね。オフィシャルのアルバムでは入ってないかもしれないけれど、ブートのライブ盤を聴くと、沢山あるんだよ。だから、彼らにとってもジャズドラマーっていうのはドラムヒーローで、ネタの宝庫だったと思うの。やっぱりドラミングの勉強要素なんじゃないかな、ルーディメンツ的なことだったり、奏法のこととか」