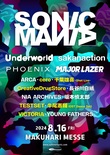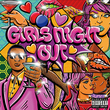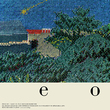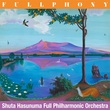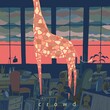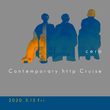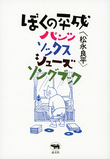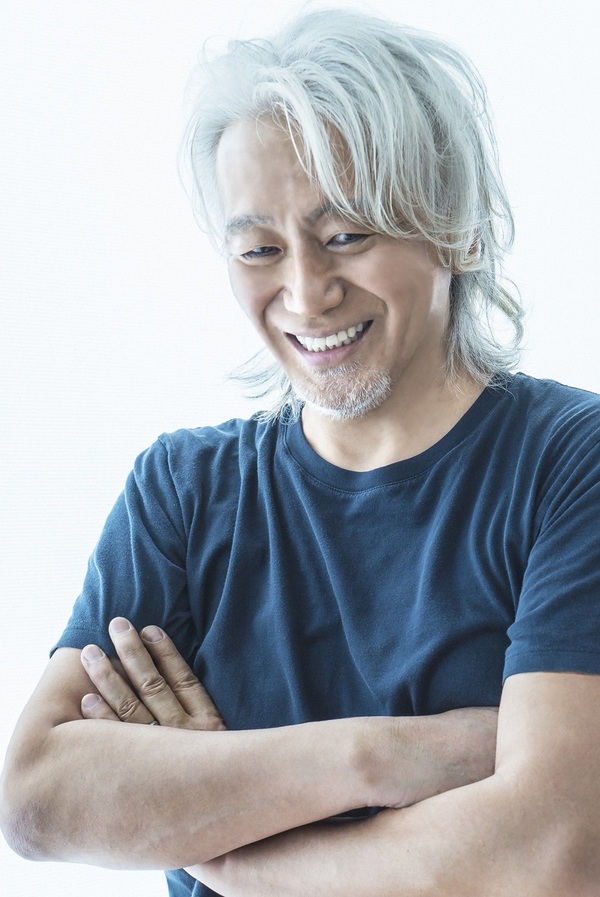『POLY LIFE MULTI SOUL』と呼吸する音の断片
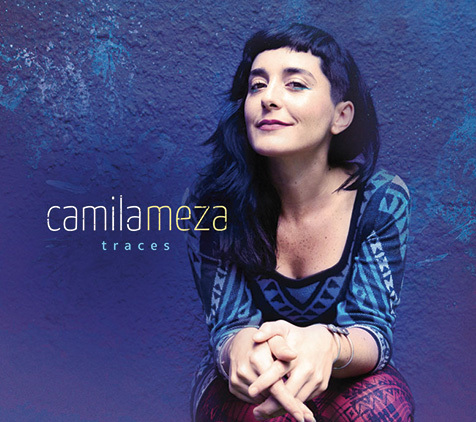
「チリ出身のネオ・フォークロア系シンガーの2016年作。NYの一線級ジャズ・ミュージシャンをフィーチャーしつつ、めちゃくちゃキャッチーでポップなんです。リズムのアプローチが“魚の骨 鳥の羽根”とまったく一緒の曲があったりしてちょっと嬉しかったです(笑)」(荒内)。
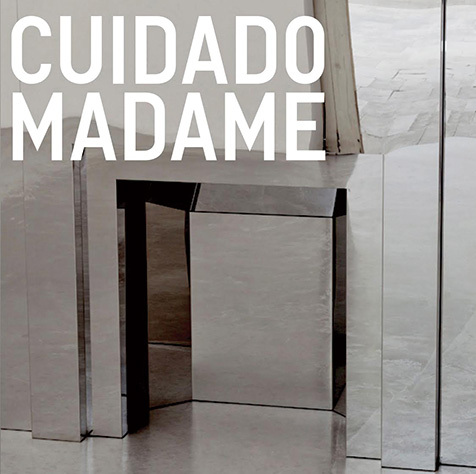
ARTO LINDSAY 『Cuidado Madame』 Northern Spy/Pヴァイン(2017)
「荒内くんが“魚の骨 鳥の羽根”のデモを持ってきた時、最初のうちは曲構造が頭で理解できなかったんです。だから、世に出ている歌もののポップスでクロスリズム構造の参考曲を探していたんですけど、そのタイミングでリリースされたこの作品を聴いて掴んだものがあって、そのインスピレーションをもとに“ベッテン・フォールズ”を書きました」(髙城)。
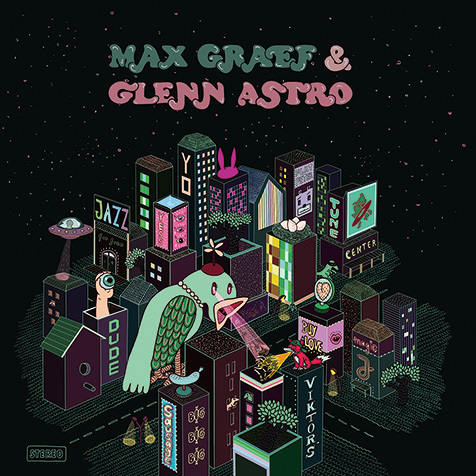
MAX GRAEF & GLENN ASTRO 『The Yard Work Simulator』 Ninja Tune/BEAT(2016)
「生ドラムのブレイクを使いながらもハウスに分類されているトラックや、ビートダウン・ハウスだったり、近年、ハウスの概念が拡張されているなかで、彼らのアプローチもユニークなんですよね」(荒内)。
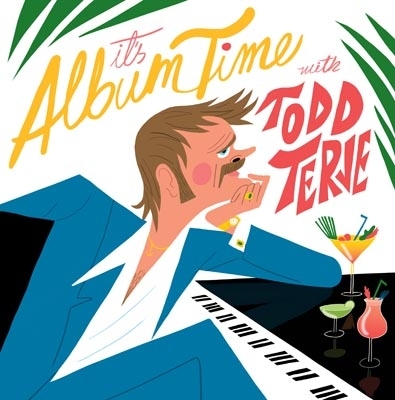
「ポリリズムを用いた曲って、実は意外なところにあったりするんですよ。このアルバムもそう。『POLY LIFE MULTI SOUL』以降の耳で聴いてみたら、曲そのもののポップさに気を取られていた“Leisure Suit Preben”でもポリリズムを使っていることに気付きましたね。聴き親しんだアルバムからポリリズムの曲を探してみるのもおもしろいかも」(髙城)。

BONOBO 『The North Borders』 Ninja Tune(2013)
生演奏を活かしたオーガニックかつエレクトロニックなアプローチと、チルでドリーミーな作風が高く評価されてきた英国のプロデューサー、ボノボことサイモン・グリーンの出世作となる一枚。「エリカ・バドゥが参加した“Heaven For The Sinner”は“Waters”とまったく同じポリリズム構造の曲だったので、自分が歌を付ける時に参考にしました」(髙城)。
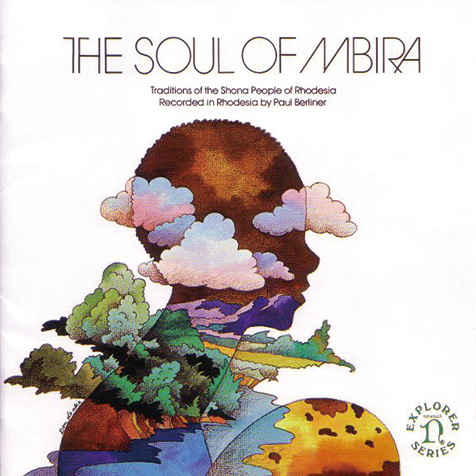
「ジンバブエのショナ族によるムビラ、つまりカリンバ、親指ピアノと呼ばれる楽器の演奏を録音したアルバムです。全編ポリリズムなんですけど、“Waters”と“魚の骨 鳥の羽根”でも使っている仕組みと同じものです。勉強のためにも聴いてましたし、カジュアルに音と戯れるスタンスにも触発されましたね」(荒内)。

「今回のアルバム制作中、個人的に参照していた作品は1枚もなかったんですけど、いちリスナーとして、このアルバムをよく聴いていました。彼らはいいコンビですよね。唾奇の生々しいリリック、ラップとSweet Williamのメロウなビートがいい具合に中和されているというか、お互いのいい部分が引き立つ関係にあるなと思います」(橋本)。
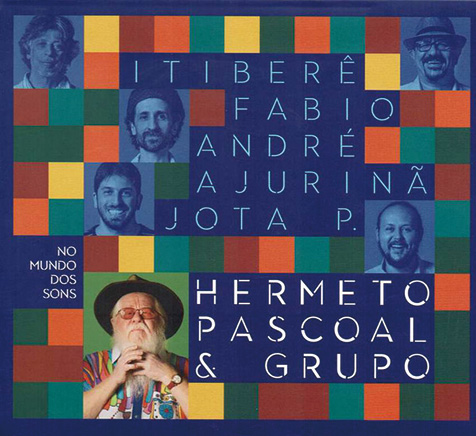
「エルメートの来日公演を去年初めて観て、生演奏の迫力に驚かされたんです。いまのceroも8人のメンバーでできることをやるという姿勢でライヴに臨んでいるし、エルメートの演奏にいまの自分たちがやっていることを重ねて、大いに刺激を受けましたね。いつか彼のようにハイパーなブラジル音楽の要素を持った曲をやってみたいです」(橋本)。
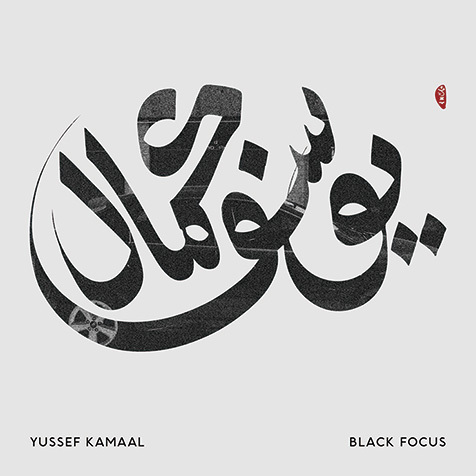
アフロ・ジャズ・バンド、ユナイテッド・ヴァイブレーションほかで活躍するドラマーのユセフ・デイズと、ヘンリー・ウー名義でジャジーな傑作トラックの数々を生み出している鍵盤奏者のカマール・ウィリアムズによるデュオ。アフロやクラブ・ミュージックに触発された新世代UKジャズが躍動するこのデビュー作は、ceroの折衷性とも響く合っている。
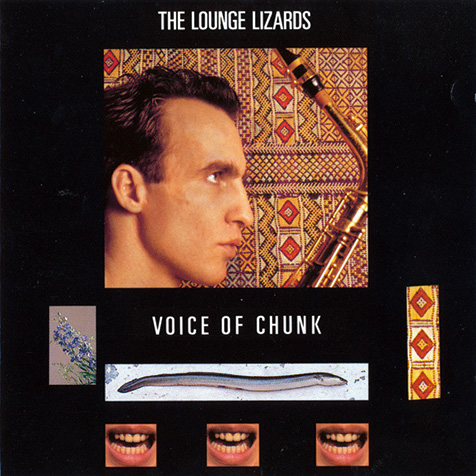
サックス奏者のジョン・ルーリー率いるNYのパンク・ジャズ・バンドによる88年作。その初期にはアート・リンゼイが在籍し、このアルバムではマーク・リーボウがギターを担当しているが、ジャズを土台にした変拍子/ポリリズム構造の楽曲に、ロックやファンク、タンゴ、ミニマル音楽など、多彩な音楽要素が溶かし込まれている。

スチャダラパーやTOKYO No.1 SOUL SETのサポートも務めるベーシストの笹沼位吉とネタンダーズの塚本功を擁するインスト・バンドの、現時点での最新オリジナル・アルバム。世界のダンスフロアを揺らした名曲“Snakes and Ladder”に甘んじず、未知なるグルーヴを求めて辿り着いた変拍子、ポリリズムの無国籍にして映像的な世界。このタイミングで再評価すべき一枚だ。
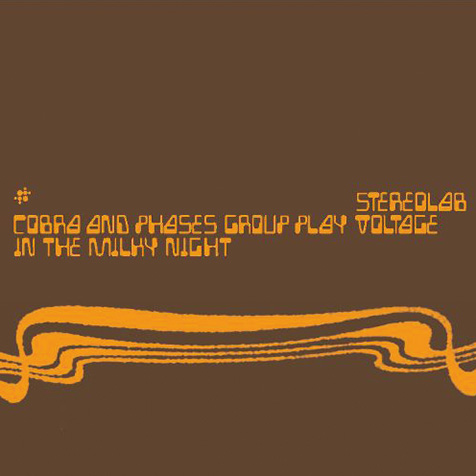
STEREOLAB 『Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night』 Elektra(1999)
90年代のUKを代表するアヴァン・ポップ・バンドがジョン・マッケンタイアとジム・オルークをプロデューサーに迎えた7作目。同時期にブラジル音楽に傾倒した盟友ハイ・ラマズによる『Snow Bug』でのチェンバー・ポップとは異なるラウンジーなアプローチで、ポリリズミックなポップ・ミュージックを生み出した傑作だ。