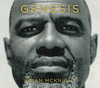エレガントな歌唱で多くのスタンダードを残してきた唯一無二のポピュラー歌手にしてアメリカ芸能界の大御所、ディオンヌ・ワーウィック。60年近いキャリアを誇る彼女の魅力をあえてソウル目線で掘り下げてみよう。
来年末で傘寿を迎えるディオンヌ・ワーウィック。1940年12月12日、ニュージャージー州イーストオレンジ生まれの彼女は、シンガーでありながら、女優、TV司会者、国際連合食糧農業機関(FAO)の親善大使などとしても活躍し、過日の第61回グラミー賞では〈特別功労賞生涯業績賞〉を授かった。ホイットニー・ヒューストンの従姉妹でもあり、アレサ・フランクリン、ダイアナ・ロス、パティ・ラベル、グラディス・ナイトらと〈ソウル・ディーヴァ〉と並び称されることも多い。
だが、その個性は他のディーヴァたちと少し違っている。まず、ソウルフルという形容があまり似合わない。〈黒い真珠〉とも呼ばれた彼女の雰囲気はエレガントで、特に初期の楽曲は、ソウル、ポップス、ジャズ、ボサノヴァなどの要素をブレンドした、万人受けするミドル・オブ・ザ・ロード路線。62年に放ったデビュー・ヒット“Don't Make Me Over”を筆頭に、“Walk On By”“Reach Out For Me”“Alfie”“I Say A Little Player”“Do You Know The Way To San Jose”など、バート・バカラック&ハル・デヴィッドの作となるセプター時代のヒットは、“This Girl's In Love With You”がイージーリスニングのチャートでも上位をマークしたように、同時代のA&M作品にも通じるライトなポップスという趣だった。60年代のディオンヌはバカラック&デヴィッドの世界を体現するポピュラー歌手であり、それは現在に至るまで彼女のパブリック・イメージとして定着している。
とはいえ、後にスウィート・インスピレーションズとなるドリンカード・シンガーズにて、叔母のシシー・ヒューストンや妹ディー・ディー、義理の妹ジュディ・クレイらとゴスペルを歌っていたディオンヌでもある。セプター時代にはドリンカード・シンガーズを招いたアルバムを発表し、2008年にもゴスペル楽曲集『Why We Sing』を出すなど、黒人シンガーとしての消しようがないルーツも明らかにしてきた。バカラック&デヴィッドの曲では伸びやかな高音域の歌声が目立っていたが、同時にゴスペル由来のザラついた声をふと放つことで、曲そのものが持つ以上の情緒を醸し出すこともあった。
そうしたゴスペル感覚は、『Soulful』と銘打った南部録音のアルバム(69年)を経て、70年代前半のワーナー・ブラザーズ移籍後にソウルに接近しはじめてから俄然活きてくる。セカンド・ネームの綴りをWarwickからWarwickeにしていたのも音楽性の変化を意識してのことだろう。移籍直後こそ旧知のバカラック&デヴィッドが手掛けていたが、以降同社ではブライアン・ホランド&ラモント・ドジャー、ジェリー・ラガヴォイ、トム・ベルらと組んだソウル・アルバムを発表。この時期には初の全米ポップ・チャート1位となったスピナーズとの共演曲“Then Came You”が誕生している。そしてアイザック・ヘイズとの共演盤を挿んで、“Deja Vu”などのヒットで好調にスタートを切った79年以降のアリスタ時代は、AOR勢とのコラボやバカラックとの再会もありながら、ルーサー・ヴァンドロスやカシーフと組んでR&Bの最前線にも躍り出た。

90年代以降はセルフ・カヴァーやデュエット、ブラジル音楽集などの企画盤が中心となるが、この20年近くは現行アーバン・シーンを担う息子デイモン・エリオットと歩んだ歴史と言っていいのかもしれない。今回5年ぶりにリリースされた新作『She's Back』もデイモンとその相棒のテディ・ハーモンがメインで制作。デュエット+セルフ・カヴァーだった前作『Feels So Good』(2014年)の流れを汲みつつ、ルーサー・ヴァンドロス、ジェラルド・リヴァート、ラサーン・パターソンらの隠れ名曲を含むカヴァーのチョイスやゲストの人選がR&B寄りとなった内容は、ディオンヌがそこの住人であることを改めて伝えるかのようでもある。
アトランティック・スター“Am I Dreaming”をトラップ・ビート入りでミュージック・ソウルチャイルドとデュエットした先行カットをはじめ、ケニー・ラティモアを招いてのテリー・キャリアー“What Color Is Love”、ケヴォン・エドモンズと歌うジェイムス・イングラム&パティ・オースティンの“How Do You Keep The Music Playing”、ブライアン・マックナイトが制作も含めて参加した“Forever In My Heart”など、狙いどころは明らか。セルフ・カヴァーの“Deja Vu”ではクレイジー・ボーンがエレガントな名曲にギャングスタなふりをして神のように愛を説く。今回はDisc-2に98年のセルフ・カヴァー集『Dionne Sings Dionne』(デイモンらが制作)のリマスター版が付いてくるが、それはタイリースやエル・デバージとのデュエットを含む同作が『She's Back』本編のコンセプトに近いからなのかもしれない。
一方では、昨年クリスマス・ソングで共演したフィジーとデュエットしたり、ロブ・シュロックの制作でドゥービー・ブラザーズの曲をカヴァーするなど、ディオンヌらしいクロスオーヴァー感もある。それでも、終盤ではバカラック&デヴィッド時代の曲や当時お蔵入りになったアシュフォード&シンプソン作の曲をジュビレーション・クワイアと歌ってゴスペルに着地。そんな部分に〈She's Back〉と謳った真意を求めるのも間違いではないだろう。 *林 剛
ディオンヌの王道的な作品。
『She's Back』に参加したアーティストの作品を一部紹介。